新潟県工業技術総合研究所は、工業系の技術支援機関です。
所長ブログ
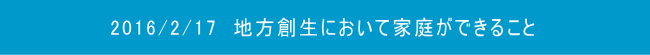
前回、「地方創生」とは「地方の人口減少」が根底にあると書いた。
そして、地方の人口減少を食い止めることに関して国が行えることは各種の制度や補助金などの支援策であり、実行主体は地方自治体や地方大学、地域、あるいは個々の家庭であるとも書いた。そこで、人口減対策には産業活性化が重要であり、そのためには優秀な人材を地域に残すことが必要で、県内の企業へ大学生を連れて巡る「新潟の成長産業体験ツアー(通称バスツアー)」を行っていることを紹介した。
前回ブログの最後に、次回は、「地方創生において家庭ができること」(出生率アップの話ではない)を書くと明言したので、そろそろ(かなり遅いが)書かなくてはならないリミットとなってきた(3月末で退職なので....)。
地方創生すなわち人口減対策で、家庭でできることと言って思い浮かぶのは、単純には出生率のアップであろうが、その課題に関する対策は国も含め各自治体で子育て支援をいろいろ考えているし、当方があれこれ言う立場にはない。
なお、産業支援の立場の人間が人口減対策において「家庭のこと」に言及するのは少々場違いなので、今回は「一家庭人」としての立場で持論と経験談を書きたいと思う。
先の成長産業体験ツアー(バスツアー)の企画段階でも話題になったのだが、学生が就職を決める際に誰からの言葉に一番影響を受けると皆さんは思われるであろうか。「先輩?」、「就職担当の先生?」、「口コミ?」.....などいろいろ意見があったが、どうやら最も影響のある人物は「親」特に「母親」らしいのである(あくまで、らしい)。二十歳過ぎの大人が母親の意見にしたがうの?といぶかる方も多いと思うが、ちょっと自らの若いころのことを思い出してほしい。「〇〇会社を受けようと思う」と親に告げたとしよう、お母さんの第一声は、「そんな会社知らないわよ。もっと有名な会社を受けなさいよ。」(多少言い方は違うだろうが)ではなかっただろうか。知っている会社なら「いいじゃない。大きいとこだし安心ね。」となったはずである。たとえ、お父さんが、「ああ、あそこか。いいんじゃないか」と言ったとしても、お母さんが知らない会社なら、「お父さんはいいの!黙ってらっしゃい。」とTV番組の様な光景が少なからずあったはずである(我が家だけか?)。
最近は私らの時代よりずっと少子化(一人っ子も多い)であるわけであるから、母親の発言はいっそう迫力を増しているかもしれない。
いずれにせよ、親の意見には従わないように見えながらも、冷や酒のように後から効いてくるようである。
というわけで、地元大学の学生さんに地元(新潟出身)に残ってもらうには、あるいは首都圏の大学から地元に戻ってもらうには、親御さんにも新潟の優良な企業を知ってもらわなくてはならないのである。そこで、成長産業体験ツアーは次の段階として、親御さんの県内企業視察も念頭に入れている。
ということで、「地方創生(人口減対策)で家庭できること」とは、親御さんが大企業ばかりに関心を持たず、地域の優良な企業を知り、子供さんたちに勧めていただくことなのである。
私の住む地域の会合で、就職期の子供を持つお父さんに「お宅のお子さんはどこに就職させたいの?」と聞くと、大抵は、「子供を縛っても悪いから、好きなところへ行っていいよと言っている。」と返ってくる。話の取り方によれば「ものかわりのいい親」にも思えるが、私に言わせれば、「子供は親の期待に沿おうとしているもの、親としての希望はちゃんと伝えるべき。」なのである。
ちなみに、私事ではあるが、私には子供(男)が二人おり、二人とも地元大学を卒業し、地元に就職している。小さい時から、「高校はあそこに行ってほしいな」、大学は「県内大学以外はダメよ」、就職も「県内できれば家に近いところね」と、常にこちらの希望を発信してきた。運よくか(人に言わせれば)洗脳か?わからないが、今のところ希望通りになっている。子供の可能性を親が摘んでいのかという意見も聞こえそうであるが、要は皆が幸せなら(と、思いたい)良いのである。
というわけで、早い話、私は早いうちから地域の人口減対策に貢献してきた(それどころか他県から息子の嫁さんをもらったので県民が一名増加した)。ちなみに、当家は家内より私の発言力が強い(つもり)と自負している。
でも正直、息子たちを地元に残したがった本当の理由はお察しのとおり「地域貢献」でも「人口減対策」でもない。というか、そもそも当時にそんな高尚な理念も持ち合わせていなかった。
本当の理由は、至って簡単。息子たちの子供(すなわち孫)の養育と自分たちの老後を考えてのことである。私たち夫婦は共働きなので、息子たちは私の両親(すなわちジジ、ババ)に昼間は面倒を見てもらった。そのために、実家(長岡)の近く家を建て、私は新潟の職場まで通い続けたのである。そして次は息子たちの子供を面倒見るのが、私ら夫婦の任務と思っている。いや、任務というより本音は「孫の面倒を見たーい!」といっても過言ではない。私が目指すは最強の「育ジイ」である(何が最強かはわからないが(汗))。
親御さんが「新潟に残ってほしいなぁ」とちょっと本音をつぶやくことが、少なくても人口流出の歯止めにならないだろうか。ものわかりのいい親から「素の親」になってはいかがだろう。私は日本の昔の家族形態は子育てという面で理にかなっていると思う。でも同居で無くてももよい。次世代に渡って子育てを回していければ良いのである。そのためには、地域における優秀な若い世代の働き場所の確保(すなわち産業の活性化)が行政の大きな課題でもある。
<バックナンバー>
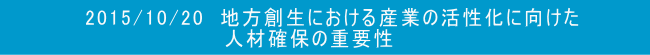
第三次安倍改造内閣が10月7日発足した。第二次安倍内閣の時から「地方創生」が重要課題となり、当時、石破氏が「地方創生担当大臣」に起用されたのはまだ記憶に新しいところだ。
さて、「地方創生」とは、そもそもなんなのか。そんなのは知っているわとの声が聞こえそうではあるが、ここはあえておさらいの意味も込めて調べてみると、実は明確な地方創生の定義は無いようである。「地域の活性化」「地域の振興」という幅広い意味合いで使われており、その施策も「農業」「観光」「科学技術のイノベーション」など、多岐にわたる。わかりやすい言葉では「まち・ひと・しごと創生」とも表現している。
そもそも、「地方創生」が安倍内閣によって提唱された背景には「地方の人口減少」にある。少子化のなかで首都圏への人口集中による地方の過疎化を食い止め、地方の自発的かつ自立的な活性化を促すことが最終目的ということだ。
では、地方の人口減少を食い止める「地方創生」には、何が必要か、何をしなくてはならないかということであるが、政府のできることは農業を含めた地方の産業活性化のための補助金や、公共事業助成、各種法整備という後方支援である。実際に行動に移して「人口流出を食い止める」のは、地方自治体や大学、地域、あるいは個々の家庭の役割である。
地方の人口減は県・市町村にとっては最重要課題で、様々な対策(雇用の創出や若者の創業支援・定住支援など)を行っているが、ここにきて大学にも大きな動きがある。文部科学省は大学の大改革を行おうとしている。国立大学を、1)卓越した教育研究 2)専門分野に優れた教育研究 3)地域貢献 の三つのタイプに分け、個々の大学の使命・役割を再定義しようというものである。県内には国立系大学は三校あるが、そのうち二校は理工系大学あるいは理工系学部を有している。こうした地方の理工系大学(学部)には「地域貢献」が強く求められている。ここで言う理工系大学の「地域貢献」とは、たやすく言えば「地方の大学は卒業生を都会に就職させずに、地域企業に就職させ、産業の活性化と人口流出の減少へ貢献せよ」も意味している。そして、さらには「地方の企業へ大学の研究成果を移転して、新たな産業・事業創出、そしてベンチャー企業の創出に貢献せよ」とも言っていると解釈できる。
今、企業、大学、工技総研は「産学官」で連携し、県内の企業へバスで学生を連れて回る「新潟の成長産業体験ツアー」を実施している。そもそものきっかけはある企業へ訪問した際にその会社の就職担当の方から、「なかなか学生が受けに来てくれない。特に国立大学からは...」という相談を受けたのがきっかけである。「頼まれたら断らない」を信条としている当方としては、すぐに新潟大学工学部の知り合いの先生(大学院の恩師でもある)に相談した。上記の大学の事情もあってか、先生からはすぐに「学生の企業見学会をやりましょう」というお返事をいただいた。そもそも卒業生が県内企業に就職しないのは、県内に優良な企業があることすら知らないからだという共通認識ができ、相談のあった企業担当者と大学、工技総研が打ち合わせを重ね「有意義な工場見学会」となる様、様々な工夫をした。昨年の12月に1回目(2社)を実施し、その新聞記事を見た他の企業の社長から「ぜひうちにも」と頼まれて、2回目、3回目と訪問企業を増やしていった。ちょうど学生も就職を意識する時期であったので、10人限定のバスツアーは有意義なものとなった。学生へのアンケートを見ると、全員が「また機会があったら参加したい」と上々の反応である。「新潟の企業に関心を持つようになった」「新潟県内にこんな素晴らしい企業があるとは知らなかった」というコメントもあり、予算も無しに始めた(企業に負担いただいた)事業としては、上出来である。
「地方創生」は「産業の活性化」無くしてあり得ない。そして産業の活性化は「優秀な人材確保」なくしてはありえない。だからこそ、県内大学を卒業した優秀な学生を地元へ就職してもらう「きっかけ作り」が重要である。就労人口対策、人口減対策は直接的には当研究所の業務ではないが、「産業の活性化」は当所のミッションである。それがゆえ、当方は全力で取り組んでいる。なお、予算化した事業では無いので、今のところ当所では相談を受けた「所長担当」の事業である。先の相談のあった企業の担当者がそれ以降も多大な協力をしてくださっているので続いているといっても過言ではない。
今年も11月から2月までに3回を予定している。一人でも多くの学生が県内企業へ就職してくれることを期待している。
ちなみに、相談のあった先の企業は、今年の採用は良い人材が多く応募してくれたので、もったいなくて予定数を超えて採用したと専務は嬉しそうに語っておられた。これがバスツアーの直接的な効果というのは早急であるが、ツアー受け入れを行った企業担当者のこれまでのやり方やホームページの見せ方などに気づきを与えるという間接的な効果があり、応募増に繋がっているようである。今後は、直接的な効果もが出てくるであろう。
次回(4回目)以降は「工学部主催」から「新潟大学主催」というお墨付きをいただいた。大学改革の中で、新潟大学としてもこの事業に大いに期待していることの表れであろう。
次回は、「地方創生において家庭ができること」(出生率アップの話ではない)を書こうと思う。
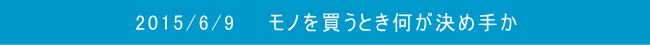
またまた、更新が滞ってしまった。もう、言い訳はやめよう。
さて、本題。人はモノを買うとき何が決め手になっているだろう。機能?デザイン?それとも値段?...買うものによって判断基準は違うかもしれない。服ならデザイン優先、電化製品なら機能が優先かもしれない。では、クルマの場合はどうか。最近は、外車がかなり安くなり、街中でも多くの外車を見るようになった。確かにおしゃれなフランス車やイタリヤ車、走りが良いとの評判のドイツ車など人気がある様である。3年半ほど前に、自分の車の買い替え時に、実を言えば外車も検討してしまった。「しまった」と表現したのは、職員には「日本経済の活性化のため日本車を買うべきだ」と飲み会で豪語した手前、検討したことすら恥ずべきことだからである。実際には職員もかなり外車に乗る者が多いので、当方の叫びは単なる「遠吠え」に終わっているが。
で、何を買ったのかというと、国内メーカーの海外生産車なのである。一般に言う「逆輸入車」ではない。「逆輸入車」とは、日本で作って輸出した外国仕様車を日本へ再度輸入するものを指すのであって、国内メーカーが海外で作って日本で売っているものは、日本メーカーの電化製品(ほとんどは中国製)と同じく、「逆輸入品」どころか「輸入品」とも言わない。車にはコンパクトカーですでにそういう車がいくつかある。ほとんどの人はそれを気にしていないというか、知らないで購入している場合もある。で、当方のクルマはイギリス製なのである。ヨーロッパ車の走りの良さに加わり、国内メーカーの品質管理で作られている。走りの良いヨーロッパ車が欲しかった私のニーズに見事に合っていた。
しかし、この車の購入の決め手はクルマ本体ではない。実は担当した営業マンの接客姿勢と豊富な知識が決め手であった。彼は、決して低姿勢でお客に媚びるような接客はしない。また、値引きでつなぎとめようともしない。その代り、こちらの質問(一応、自動車工学を勉強したから専門的な質問もする)に間髪入れず、正確な回答を出す。話していて楽しいのである。結局、展示車も試乗車もないカタログだけで購入を決めた。しかも他の販売店から見積もりも取らず、1回の見積もり額で即決である(太っ腹?)。ある意味、顔も見ず、会ったこともない人と見合い写真で結婚を決めたようなものである。
彼は、購入後のフォローも完璧である。やはりヨーロッパ車。国内メーカーと言いながらも、細かな不具合は結構出た。しかし、そのたびにこちらの不満を解消しようと努力してくれた。結局は治らない(運転席周りのビビり音)もあるが、かなり何度もばらしては見てくれたので、努力に満足している。
3月には家内のクルマを購入することになったが、家内曰く、「○○さんから買える車なら何でもいい」なのである。家内も彼のファンである。
人はモノを買うときに、様々な優先項目がある。クルマなら多くの場合は、車のタイプと予算をもとにいくつかのメーカーのクルマを比較して買うのが普通と思う。昔は自分もそうであった。クルマ本体や価格より「営業マン」で購入を決める。そうさせる営業マンはすごい。クルマに限らず、人はモノを買うとき、機能やデザインも重要だが、実は「満足感」が一番重要なのである。それが「営業マン」であるなら、「サービス精神」の神髄がそこにある。

ちょっと変な表題であるが、仕事とは言われたことをするだけで無く、自ら仕事を見つけることで、より質の高い成果を生むということを書きたいのである。
多くの仕事は、すでに決まった分掌や、上司からの指示で行う仕事がほとんどである。しかし、書類一つを作るにも、言われたこと以外に「この資料を用意すればよりわかりやすいな」とか、「指示の内容より、この内容の方が良いから提案してみよう」などと、工夫して仕事をしてくれる人がいる。こういう人が、私の思う「出来る人」なのである。言われたことしかしない人、さらには言われたこともきちんと出来ないヒトは「人に役立つ仕事」というところからはほど遠く、且つ、自分自身も満足感を得られていないヒトだと思う。「出来る人」というのは、「人の役に立とうとして行った仕事ぶりの結果」として生まれる評価だ。
本当かどうかはわからないが、ある記事によれば、会社には2割の出来る人、6割の普通の人、2割の仕事の出来ない人で成り立っているそうである。「収益」が判断材料になる企業においては、2割の出来る人が、2割の出来ない人を養っているということになってしまう(6割はそれなりに自分の分は稼いでいるということか)。さて、公務員の場合はというと・・・・「収益」という評価は無いから、書き様が無いので止めておく。
当研究所に話を移す。当所には大きく二つの職種に分けられる職員がいる。そう、研究職(技術職)と一般職(事務職)である。そして、一般職には、正規職員と臨時的職員(産休、病休の補充職員など)の方、そして非常勤職員(一般的に言えばアルバイト職員)の方がいる。研究職にも臨時職員もいるが、今日は事務職の非常勤職員の話である。
今年、7月に非常勤職員の一人が、新たに採用した方に替わった。この方の仕事としては、試験成績書の郵送作業や回覧文書の整理、郵便物の収受、庶務用品の購入など、いろいろな庶務関係の仕事を手伝ってもらっている。職員が業務を円滑に進めるための、サポート役である。
非常勤職員はフルタイム勤務では無いこともあり、まだ子育て世代の女性の方々の応募が多い。結婚されいったん職を離れたが、子育てに慣れてきたので家事に影響無い範囲で働きたいという方の応募が多いようである。こうした方々は独身時代にはそれなりのキャリアを積んだ方も多く、また家事や育児と仕事を両立してやりたいという意欲のある方々であるから、当然、応募者の多くは能力の高い人になる。前任者も優秀な女性で、細かな事にも気を遣ってくれ大変助かっていた。しかし、能力があるということは、こちらがお願いする仕事の内容では役不足*という心配もある。
(*誤用が多いが、正しくは「人」対して「役(仕事)」の方が不足しているという意味)
このたび新たに採用になった方も、能力・意欲が高い人である。先日も、私が講演で使う資料のグラフ作りをお願いしたが、期待以上に早く、且つこちらのイメージを的確に表したグラフを作ってくれた。ますます、役不足が心配になってしまった。でも、彼女はそんな事はおくびにも出さず、与えられた仕事を黙々とこなしている。そして、さらに感心するのが、自分で仕事を見つけて、実行していることである。彼女は、自分の能力をひけらかすこともなく職員のサポート役という立場を認識し、何をしたら職員の役に立つのかに気を配っている。まさに私の言う「出来る人」なのである。
 例を挙げたらきりが無いし、気づかずにいるものがいっぱいあるのだが、ある日、ラベルライターを使おうと思ったら、テープの幅や色がわかる様、綺麗に並べられていた(写真)。すぐに必要なテープを見つけられた事は言うまでも無い。
例を挙げたらきりが無いし、気づかずにいるものがいっぱいあるのだが、ある日、ラベルライターを使おうと思ったら、テープの幅や色がわかる様、綺麗に並べられていた(写真)。すぐに必要なテープを見つけられた事は言うまでも無い。
「出来る人」は、常に誰かの役に立つことを考えている。「出来る公務員」は常に納税者である県民や企業の役に立つことを考えていなくてはならない。
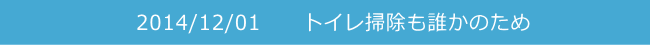
先のブログでも書いたように、私は遠距離通勤者で通勤に要する時間も長い。なので、若いときから出来るだけ終業時間までに仕事が終わる様、いくつかの仕事をパラレルで進めたり、効率を高めるために実験道具や工具の整理整頓をしたり、自分なりの工夫をしてきた(ちなみに、この習慣が料理作りの段取りにも役立っている)。整理整頓は、今や工技総研の毎月の「5S活動」に繋がり、外部の方やOBの方からもずいぶん研究室が綺麗になったとお褒めの言葉をいただくこともある。
そもそも整理好きのこともあり、そして家内が仕事を持っていることから、忙しい家内に代わり私生活でも自然に「掃除」はほとんど私の担当のようになってきた。毎日は出来ないので、土曜日の午前中はトイレも含め徹底してやった。家内は、土曜や日曜も出勤、ウィークディも帰りが私より遅いことも非常に多かった。そんなわけで、掃除のみならず夕食を作ったり、子供の世話や、洗濯なども当然のようにやって来た。子供が大きくなってからは、「出来る者が、出来る時に、出来る事をする」が我が家の暗黙のルールになり、各自が出来る家の仕事をするようになった。夕飯も早く帰った者が作る。今でも家内が遅くなる(週に1~3日)ときは、私や同居している次男も台所に立つ。
そもそも、私は昔から「これは女の仕事」「これは男の仕事」という意識が無い。まして、「夕飯作りやトイレ掃除は女の仕事」というような差別的な意識も無い。だから、男は外で働いているのだから、家に帰ったら何もしないという人の感覚はわからない。奥さんが専業主婦ならいざ知らず、共働きならするのが当然である。共働きなのに、家のことは何もしない男の人は、私にとっては異星人だ(笑)。そういう人は、「オレは女房より大変な仕事をしている」とでも言いたいのであろうか。しかし、会社で仕事が「出来る人」は、「家庭の仕事もきちんとこなす」というのが私の持論だ(私が「出来る人」かは別として(汗))。
さて、ちょっと話を戻す。私にとって、仕事も、家事も、トイレ掃除も同じ意識で「自分なりに」一生懸命する。なぜなら、仕事も家事も含め誰かの役に立つという点で同じだからである。トイレ掃除は、人によっては「負の作業」のイメージを持つひともいるようだ。しかし、綺麗なトイレは、皆が気持ちよい。だから、使う人のことを考えながら行うトイレ掃除は楽しい。職業に貴賤が無いように、家事仕事にも貴賤は無い。
話は変わるが、東京ディズニーランドのリピータはとても多い。聞くところによれば、ハード面だけで無く、スタッフの一生懸命に楽しんでもらおうとする姿勢によるところが大きい様である。そして、実は隠れた理由がもう一つある。「カストーディアルキャスト」と呼ばれる、主に清掃担当を行うスタッフの仕事ぶりと笑顔なのだそうだ。彼ら、彼女らはトイレ掃除にも「誇り持って」取り組んでいる。仕事でやっているだけと言えば、それまでだが、彼らには「使う人のため」という共通の思いがある。
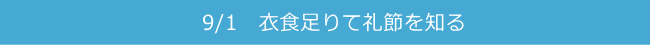
またまた、ブログの更新が滞ってしまった。文章を書くときはまとまった時間が取れないとなかなか手に付かず、お盆は来客も無く更新できるかと思ったら、県庁からの宿題などに費やされ、結局今日になってしまった。今日から9月、もう秋である。
私は自宅が長岡市内にあるので、バスと新幹線、そして徒歩といろいろな交通手段を使いながら、待ち時間を含め片道1時間40分くらい掛けて通勤をしている。東京なら、郊外からその程度の時間を使って通勤する人は多いようであるが、新潟でこれだけ通勤時間を掛ける人はそう多くはいないと思う。我ながら良く通っていると思うが、歳のせいか、若い頃に比べると長距離通勤も疲れる様になってしまった。あと約1年半がんばらねば。
さて、今回の話は通勤時間の長いことをぼやくのが趣旨ではない。これだけ長い通勤をしていると、じつに様々な不快な場面に遭遇することがある。満員なのにバスの二人掛け席を一人で占領するヒト、新幹線エスカレータでの「歩行禁止注意」を無視して人にぶつかりながら降りていくヒト、歩道の真ん中を傍若無人に疾走する自転車に乗るヒト、などなどマナーを知らないヒトの例を挙げたらきりが無い。しかもほとんどが若者である。
日本人の規律正しい姿勢や人を思いやる利他的行動について、日本に来た外国人が賞賛するテレビ番組を最近見た。確かにほとんどの人は車が来なくても赤信号を守るし、新幹線ホームで列に割り込む人はまずいない。よほど、外国ではそうした決まりを守らない人が多いのか、日本人はとても規律正しく、民度が高い国民と思われているようだ。子供の頃を思い出すと、バスを待つ列も曖昧だったし、割り込みも良くある光景だった様に記憶する。日本人がきちんと列をつくり割り込まなくなったのも、道路で赤信号を守るようになったのも、ここ数十年のことのように思う。「衣食足りて礼節を知る」ということわざがあるが、日本が海外から賞賛される民度を身につけたのも、まさに日本人みんなが豊かになってからのことでは無いだろうか(飽食の時代とまで言われた)。
しかし、最近はグローバル化の影響で、近年は日本国民の貧富の格差が広がっている。特に問題なのが若者の貧困である。先の「マナーを知らない」行動をするヒトの多くは若者であった。彼らは富める親に育てられ、その生活がずーと続くと思い込んだまま大人になってしまった。勉強しなくても何かの仕事に就けて、親と同じくらいの収入があって、親と同じくらいの生活ができると思っていたはずだ。その頃、彼らには危機感は無かった。しかし、急速なグローバル化が進み、国内の製造業の中でだれでも出来る仕事は海外に流れ、知識や技能をさほど必要としない仕事は日本には残っていない。すなわち、ただ単にみんなが高校に行くから自分も進学し、目的も無く勉強もしなかった人のできる仕事は無くなってしまった。ある意味、学生の時にがんばった人しか豊かな生活を送るチャンスを得られない時代に突入した。
そうすると、これから問題になるのが「貧困の悪循環」である。親の収入の低い世帯の子供の進学率は富める世帯に比べ圧倒的に低いという調査データがある。その中には優秀であっても進学出来ない子供が含まれている。政府もようやくこの問題の解決に向け検討を始めている。人材(人財)こそが日本の資源なのだから大いにやって欲しいと思う。是非とも優秀な人材には手厚い支援をして欲しいと思う。そして、進学する側も認識をきちんともって欲しい。「大学に入ること」が目的では無い。「大学で知識を得ること」が目的なのだ。勉強するのは「良い点を取る」ためでは無く、「いい学校に行く」ためでも無い。知識を得ることで「仕事へのチャンス」を広げることである。すなわち「勉強」は「食っていくため」にするのである。自分で食っていけない人に「人のために生きる」ことは出来ない。親や学校はそのことをきちんと教えるべきだ。
話は、だいぶずれてしまった。前述の「無礼」な若者がすべて「貧困な子供」とは言わない。しかし、低所得世帯の子供の進学率が上がり、そこできちんと勉強し、豊富な知識を身につけ、そして人に役立つ仕事に従事し、豊かな生活を送れるようになって、この国に貧困の格差が無くなれば、満員のバスで席を占領する不届き者や、ぶつかりそうに歩道を疾走する自転車乗りも、すこしは少なくなるのではないかと密かに期待をしている。「衣食足りて礼節を知る」ということわざは、「管子」という人の故事から来ているそうである。欧米でもMeat and cloth makes the man.とかWell fed, well bred.ということわざがあるそうだ。衣食を心配しているようでは、他人への気配りなどできなというのは、万国共通の認識のようである。
さて、当所は技術の面で企業の皆様へサービスを提供する行政サービス機関である。職員にも「サービス精神の向上」を説き、「顧客満足」「顧客感動」に繋がる業務をしてもらうように機会があるごとに訓示している。かなり対応は良くなって来ていると自負するが、個々の職員による接遇や対応姿勢にバラツキがまだあるのは否定できない。
今、CSアンケート(顧客満足度アンケート)を、昨年利用していただいた企業様へ郵送し回答をいただいているところであるが、すでに中には対応姿勢にご不満をもたれた企業様の回答があり、管理職として大きく反省をするとともに、お詫びの気持ちで一杯だ。せっかくいただいたアンケートのご意見なので、改善に向け必ず対応をすることをお約束する。それは、優れた対応をしているほかの多くの職員のためにでもある。
ところで、東京五輪の誘致活動での滝川クリステルさんのプレゼンにより昨年の流行語大賞にもなった「おもてなし」は、当方が職員に言っている「サービス精神」と何が違うのか疑問に思い、Webで調べてみたらこんな記述があった。
○おもてなし:ホスピタリティのこと。病院(Hospital)を語源とし、対価を求めない自然発生的な対応。
○サービス:ラテン語の奴隷(Servitus)を語源とし、上下関係がはっきりした場面で用いる。このためホテルでサービスを受ければ、サービスチャージやチップなど対価が発生する。
「おもてなし」の記述は、日本人の持つ「人のために役に立つ」という利他的志向が根底にあり、「対価を求めない自然発生的」というのは、何となく理解ができるが、「サービス」の記述は、必ずしもわれわれ日本人が捕らえている言葉のイメージと完全に一致しているとは思えない。日本では「サービス」という場合も、ほとんど「おもてなし」に近い意味でとらえているように思われ、上記の記述は少し語源にこだわっているようだ。ただ、海外でのサービス(SERVICE)では確かにこの記述が成り立ちそうな場面も多いが、調べると海外でも「奉仕」という意味にも使うようで、やはり上記の記述は現在の「サービス」の意味を完全には記述していないようだ。
ただ、「サービス」と「おもてなし」は、明らかに聞いた時の語感が違う。職員に「企業の方にサービス精神をもって対応してください」と言うより、「企業の方にはおもてなしの心で対応してください」と言うほうが、職員の心に残りそうだ。
どこからか「公務員におもてなしの心なんて無理、無理!」なんて声が聞こえてきそうであるが、そう思われていると思えば思うほど、私の改革意識は高まるのである。来年のCSアンケートでは「不満回答ゼロに」と強く、強く思う。
当所の公開事業としては、産業界(企業)向けの「研究成果発表会(施設見学も含む)」や各種セミナーなどを開催している事から、普段は企業の方が来所されているが、一般の県民の方が来所される機会はほとんどない。そこで、一般公開は当研究所が行っている業務を県民の方にもっと知ってもらうということで、そもそもは始まった行事である。
確かに当研究所のPRも重要であるがのだが、それよりも「県内企業のすばらしい技術」を一般県民の方々にも知ってもらいたいのと、日本の未来を担う子供達に「科学・技術」への関心を持ってもらいたいとの目的で、当所の一般公開も県内技術を活用した「プレス技術の体験」や「プラスチック成形の体験」、「切削技術の実演」などを加え、物作りの楽しさを体験してもらえる内容へと変化させてきた。

日本のもの作りはグローバル化の中で、どんどん海外へと生産拠点が移転している。しかし、資源の無い日本は「工業製品」で外貨を稼いでエネルギーや原料を購入しなくてはならない。食料品だって、国内自給率は40%強しかなく、中国や他の諸国から輸入しているのが現実だ。いかに外貨を稼ぐ産業の発展が重要なのかが解ろうというものである。
前述のように産業構造の中で日本の産業のあり方はどんどん変わって来ている。従来のように品質の良い工業製品(電化製品など)を日本で生産して、海外に輸出するという形態はすでに崩れ、日本メーカといえども、中国やアジア諸国などの人件費の安い国外で作って、日本国内や海外で販売するという形態になっている。車についても最近では消費地である海外生産へと代わって来ている。すなわち、工業製品を国内で作るということ自体が無くなりつつあるということである。ただ、それは大量生産品や、技術が確立し設備とそれなりの作業者がいれば作れる汎用の工業製品であるということに気づくべきである。言い方が悪いが、その製品に「魂」は無い。
日本人には「優れた技能」と「より良いモノを作りたいという向上心」そしてなにより「人に喜んでもらえるものを作りたい」という「利他主義」とも言える国民性が根底にあると個人的には思っている。急成長してはいるが拝金主義の国とはもの作りの姿勢が決定的に違う点だ。
 私たちが直接には産業に関係の無い一般県民の方々を対象とした「一般公開」を行い、特に子供達に「もの作り」の楽しさ、凄さを伝えたいという意味は、そこにある。作る側が楽しくなくては、その製品を手にする人も幸せにはなれない。それは「料理」と全く同じなのだ。
私たちが直接には産業に関係の無い一般県民の方々を対象とした「一般公開」を行い、特に子供達に「もの作り」の楽しさ、凄さを伝えたいという意味は、そこにある。作る側が楽しくなくては、その製品を手にする人も幸せにはなれない。それは「料理」と全く同じなのだ。
廊下ですれ違ったあの幼い子が、走って会場へ向かって行ったあの子が、二十年後、きっと日本の産業を支えている。
さて、7月末からちょっと早い夏休みを取り、恒例の海外旅行へと行ってきた。どこにしようかと迷ったあげく、三年連続の「台湾」である。プチ海外旅行としては中国、韓国も関心が無いわけでは無いが、近年のますます反日感情が強くなっている所へ行く勇気もなく、再度、親日的で食べ物もおいしい台湾となった。台湾に行く理由は2つある。一つは「小籠包」に代表される中華料理(台湾料理)と、もう一つは、日本では一般に烏龍茶と言われている「台湾茶」の購入である。
烏龍茶は日本ではペットボトルで売られている「茶色のお茶」がなじみ深いが、その原材料の茶葉産地を見ると中国産であることが多い。確かに烏龍茶の茶樹は中国が原産であるが、中国から台湾に持ちこまれ、その後、日本統治時代の茶葉振興施策により品種改良(台湾の研究機関の功績が大きいとのこと)がなされ、今では中国烏龍茶とは全く違うと言って良いほどのお茶となっている(色も薄黄色から茶色まで様々)。どうやら中華料理も同様のようで、近年は日本やシンガポールにも支店を出している小籠包の「ある有名店」は中国本土からの観光客がいっぱいだ。本土より旨いということだと想像する。余談になるが、この小籠包の有名店は、最初に台湾へ行った10年くらい前は日本人観光客がいっぱいで、店員も日本語で対応してくれていたが、最近は中国人観光客の方が多くなったせいか、日本語の話せる店員も限られているようだ。去年、若い女性の店員が、こちらが日本人とわかるととてもうれしそうに対応してくれたことが印象に残る。すなわち、年代を問わず親日的だ。
台湾茶の話に戻そう。戦後は栽培技術、焙煎技術の改良・機械化により安定した品質の良い台湾茶が全土で広く手に入るようになった。日本ではまだ本格的な台湾茶が買える店が少なく(県内では新潟市に一軒ある)、ネット通販などでも買えるものの、良いお茶を買うなら絶対に現地へ行くしか無いと思っている。
台湾茶は半発酵茶(日本茶は無発酵茶、紅茶は完全発酵茶)で、発酵の少ないものからかなり進んだものまであり、台湾茶にはその発酵段階や茶樹、茶葉の取れた山・高度によって多くの種類が存在する。私のお気に入りは、「高山烏龍茶」や「阿里山金萱茶」「文山包種茶」などだ。阿里山金萱茶はほんのかすかなバニラの香りがするが、通販などで買うと香料を使ったモノがあるので、そういう意味でも現地購入が安心だ(ただし、現地でも香料を入れている店もある)。出来れば、「工夫茶器」を使って香りを楽しむ飲み方をして欲しい。
 実は私たちは今まで六回も台湾に行っている。そしていつも同じ店で購入している。茶葉農家から始まり焙煎工場も持っている家族経営の店で、そういう意味でも安心だ。店に行くと相手をしてくれるのは次男の呉榮峻さん。少したどたどしいながらも日本語が話せる。またそのお嫁さんがこれまたかわいい美人だ(当然、画像の左)。日本語は奥さんの方がうまいかもしれない。この店からは今はホームページでも購入出来る。
実は私たちは今まで六回も台湾に行っている。そしていつも同じ店で購入している。茶葉農家から始まり焙煎工場も持っている家族経営の店で、そういう意味でも安心だ。店に行くと相手をしてくれるのは次男の呉榮峻さん。少したどたどしいながらも日本語が話せる。またそのお嫁さんがこれまたかわいい美人だ(当然、画像の左)。日本語は奥さんの方がうまいかもしれない。この店からは今はホームページでも購入出来る。
先に書いたように、日本に統治されていたにもかかわらず台湾の人々は年齢を問わず非常に親日的で、日本へ行くことにあこがれる台湾の若者も大変多いようだ。
 実は、日本と台湾は正式な国交は無い。人口もわずか約2,300万人と少ない。なのに、東日本大震災の時に日本赤十字社に送られた義援金は最多の米国とほぼ同額の29億円超である。金額で善意を区別すべきでは無いが、人口、GDPを考えたらその善意と日本への思いの大きさに目頭が熱くなる。こんなに親日的で日本を応援してくれている台湾を日本人はどのくらい知っているのだろう。もっともっと知って欲しいと思うのである。「台湾茶を知ろう!」の意味はそこにある。もちろん台湾はお茶や中華料理だけでは無い。有名な「Taipei101」や「淡水」観光など見所もいっぱいなのだ。
実は、日本と台湾は正式な国交は無い。人口もわずか約2,300万人と少ない。なのに、東日本大震災の時に日本赤十字社に送られた義援金は最多の米国とほぼ同額の29億円超である。金額で善意を区別すべきでは無いが、人口、GDPを考えたらその善意と日本への思いの大きさに目頭が熱くなる。こんなに親日的で日本を応援してくれている台湾を日本人はどのくらい知っているのだろう。もっともっと知って欲しいと思うのである。「台湾茶を知ろう!」の意味はそこにある。もちろん台湾はお茶や中華料理だけでは無い。有名な「Taipei101」や「淡水」観光など見所もいっぱいなのだ。
(画像は淡水の「情人橋」(バレンタインディに開通したことから別名:恋人橋)よりの夕日)
なかなか見つからないゴミが、ある地点からいきなり急増する。缶はもとより、コンビニで買って食べた容器の残骸、果ては赤ちゃんのおむつが風雨で分散したと思われる綿状の塊........。唖然として言葉も出ない。
私の住居は越後国営丘陵公園に近い町にあり、この道路は国営公園から来た道が国道に上がるためのインターチェンジのようなカーブになる。カーブの遠心力を利用して藪にゴミを捨てるというわけだ。時々、藪に入らず路面に転がっていることもある。見えるゴミは、ときどき地元の産廃処理会社の社長が拾ってくださっていると聞く。
東日本大震災では日本人の秩序の良さ、マナーの良さをたたえる外国メディアが多かった。日本人の民度の高さに世界中が驚嘆した。日本を訪れた外国人のブログでも、日本はゴミが少なく清潔なことを賞賛する記述が多い。しかし現実は....。
ゴミを捨てているのが日本人か外国人かは解らない。しかし、言えることは一つ。たばこの吸い殻と同様に捨てたのはゴミだけでは無い。その人の「良心」もなのだ。シンガポールの様に「ゴミのポイ捨て、即罰金」にしないと、ポイ捨てが無くならない国になってしまったのだろうか。
クリーン作戦から一ヶ月、すでに多くの「誰かの良心」が捨てられている。
出張の主目的は「県内企業の航空機産業」と「植物工場装置」のPRである。成果としては、航空機だけに限らず、機械など工業製品全般にわたる「工業ビジネス研究会(交流会)」のようなものを、両地域の企業で立ち上げ、お互いの情報交換をしながら、新潟の工業製品や部品をロシア側へ供給するビジネスを検討することとなった。また、植物工場については、PRした食品会社の関係者ら(約20名)は大いに関心がありそうで、何人かは新潟まで来て現在実証試験中のキャビネット型植物工場や、地中熱・雪冷熱利用で実証試験中のコンテナ式植物工場を視察したい様な話もでた。
いずれも今後の展開を期待したい。
さて、ハバロフスク出張は十数年前に行って以来の久しぶりであるが、なんと泊まったホテルは同じインツーリストホテルであった。町の風景といい、ホテルの内外装といい、一見するだけでは、ほとんど変わった様子が無い。違いと言えば、昔は日本の中古車(しかも店名の入ったままのバン、小型トラック)が多かったが、今はほとんど無く、新車から使っている様な日本車が多かった。ただ、砂塵と泥をつけたままで、ほとんどのクルマが真っ茶色。洗ってもすぐに汚くなるのでまだそのままとのこと。本格的に春になり道路補修と清掃が終わると綺麗にするようだ。確かに、まだ冬(の終わり?)なのかハバロフスクは緑が全くなく、街路樹も公園も茶色のままだ。緑が息吹くと綺麗な街になるとのこと。
滞在した期間の気温は5℃~8℃位で新潟より少し寒い位であったが、たまたま比較的暖かい日が続いただけで、本来は0℃~3℃のようだ。アムール川の氷もまだすべては溶けずに川を覆っていた。1回目のハバロフスク訪問時は時期が12月末だったので、アムール川も凍り付いており、川の上を数十メートル歩いた記憶がある。
ロシアというと旧共産圏のイメージを払拭出来ない方もいる(当方もそうであったが)と思うが、現在のロシアは堅苦しさも無く、外観は変わらないものの内装がおしゃれな飲食店も多い。アムール川岸も昔はアル中のたまり場だったそうだが、今は綺麗に整備され市民の憩いの場になっていた。日本よりスピードが遅い感じはあるが着実に発展している。
ロシアとの関係では領土問題などまだ解決していない課題はあるものの、個人レベルでは親日的である。細かなところでは日本の感覚で期待するとがっかりすることもあるかもしれないが、そこはお国柄と割り切りたい。親日的であるということは、ビジネス面でとらえれば、反日運動・ボイコット運動は起きそうに無く、リスクが小さい。新潟の製品を売って行くには安定した市場ととらえることも出来るのでは無いかと思う。
観光交流、ビジネス交流も含め今後の展開を期待したい。
さて、当研究所ではこの時期に毎年「CSアンケート」を実施している。直近2年間に当研究所をご利用いただいた事業所様へ送り、返送していただくという形であるが、今年は約1200社にお送りし、現在約36%の企業から回答をいただいている。
現在は集計中であるのでまだ最終の数値ではないが、今年も例年同様に、「職員の対応」としては「満足」「やや満足」を合わせて9割以上になる。依頼試験や機器貸し付けなどサービスごとの満足度の数値もほぼそれぞれ9割近くとなっている。
ただ、ここでこの数値をどう見るかが重要なポイントである。昨年度のアンケート結果では、ある外部の方から「満足度が9割以上とはすばらしい」とおっしゃっていただいた。お褒めの言葉は誠にうれしいし、がんばってくれている職員に感謝したい。しかし、ただそれで満足しているわけにはいかない。研修のお陰もあり、確かに、若い職員をはじめ多くの職員の対応は以前に比べ格段に良くなっており、昔のような「お役所的」な対応は非常に少なくなっていると思う(それでも完全にゼロでは無いが)。接遇面以外の試験業務、技術支援など当所の基本サービスの質も優秀な職員が採用されてきており、かなり上がってきているとも思う。しかし、それでも「やや不満」「不満」は計2%ありゼロでは無い。管理職としては、9割超えの満足度の数値に満足せず、2%のご不満にどう対応するかが重要と思っている。
民間企業も含めどんな分野でも顧客の不満を0%にすることは出来ないかもしれない。たとえミシュランの三つ星レストランでも「不満」という人がゼロでは無いだろう。しかし、ゼロにはならないにしても、ゼロにする努力をする事こそが大切であり、その努力をすることで「不満」はゼロにならなくても、「満足」の評価をしていたお客様がその上の「感動」の評価に変わるものと思う。
「満足」が「対価相応」と解釈すれば、「感動」とは「そこまでしてくれたの!」という驚きである。当所の業務の中での「依頼試験」を例に取ろう。企業から依頼された試験を約束の日までに約束した通りの内容で結果を出せば、企業の「満足」は得られるかもしれない。しかしさらに、「期日より早く終わらせた」、「途中経過の報告をした」、「試験結果の悪かった原因まで調べておいた」などのちょっとした気遣いや対応が加わると「満足」が「感動」に変わるのでは無いだろうか。それができる人は、前回ブログで書いた「ヒトは人のために生きている」という姿勢と繋がる。
サービスの向上は仕組み作りやマニュアル整備だけで達成できるものではない。職員ひとりひとりの意思によって、真の顧客感動を得ることができるものと考えている。
今日、福島県庁へ応援に行っていた職員が2ヶ月ぶりに戻ってきた。被災地での復興のための業務はさぞかし大変だったと思うし、慣れない地での生活も寂しいものがあったと思う。今日は、関係部署職員で彼女の「お疲れ様会」がある。当地の様子をしっかり聞いて、自分なりに出来る東北応援を再度思案してみたいと考えている。
こうした業務を「仕事」と考えれば、人によっては苦痛に感ずる人もいるかもしれない。しかし、「東北のため」「人のため」と考えれば、また違った意欲が生まれる。あるいは、「仕事」と思って赴任しても、仕事をしているうちに「人のため」という感覚に変化することもあるだろう。
「仕事」を何のためにするのかと聞かれて、人はどの様な言葉を返すのであろうか。「生活のため」、「お金のため」などというのは容易に想像がつく。「この仕事が好きだから」、「スキルアップのために」などというのもあるかもしれない。突飛なところでは「暇だから」などと言ううらやましいものもありかもしれない。
しかし、一般的には仕事が無ければ生活が成り立たない人がほとんどのはずであるから、「生活のため」というのは、ほとんどすべての人に当てはまる。要は、それ以外にどんな目的、意識があるかである。企業は利益を上げるのが目的という人がいる。行政はそうした共通の目的が無いから真剣さが足りないという人がいる。でも、そうであろうか。企業であれ、行政であれ、最終的には「人の役に立つため」に仕事をしているのだと思いたい。
企業は利益を挙げるのが目的と言うけれど、最終的に社会(人)に役立たない仕事をしている企業は潰れる。社会(人)の役に立つ商品やサービスを提供するから、結果として利益を生んでいるのだと思う。お金に取り憑かれたヒトや企業は、ますます欲を出し、最後は非社会的な行動で事件沙汰になる事例は枚挙にいとまが無い。そうならなくても、そういう仕事の仕方をしているヒトは、どこまで行っても満足心を得られない。周りから目立つことを目的に仕事をしているヒトも同じだ。
ヒトは人のために行動し、その人からこっそりとでも感謝されたとき、お金にも勝る満足感・達成感を得ることが出来る。そしてそれは、周りの人も自分も幸せになれるということである。それは、個人だけで無く企業であれ、行政であれ同じだ。自分や自分たちの欲望(お金や名誉欲)のために仕事をしていないか、時々振り返ることが大切である。
私は思う、「ヒトは人のために生きている」。
(今回より、随筆調で書きます。ご容赦ください。)
その旅行後に、燃料漏れトラブルやバッテリートラブルの重大インシデントの発生で787は運航停止、さらには新規納入の見合わせという事態になり、今思えばちょっと危険な目に遭う可能性もあったなと複雑な思いがあります。
さて、運航停止、新規納入停止という事の影響は、単にJALやANAなどの運航会社に影響を及ぼすだけではありません。準日本製と言われるように787の機体の35%は日本の部材や製品が使われています。実は、内装品になりますがギャレイやラバトリー(トイレ)などはユニットで新潟県内の企業が一手に製造しており、さらにその一部を下請けしている企業も多くあります。今回の騒動は決して、航空機メーカ、電池メーカの一大事では済まされません。3年遅れでようやく就航し、これから本格生産という期待が出てきていた時だけに、誠に気に掛かる出来事です。
アクシデントの中でも一番の重大事がバッテリー火災で、その製造元が日本メーカということで、原因次第では、787を準日本製とアピールしていたのが裏目に出る可能性もありますが、バッテリーはフランスのメーカへ納入され、電源制御回路はそこで組み込まれており、バッテリーだけの問題では無いのではないかと思って(期待して?)います。さらには、日本製品と言われているバッテリーの内部部品やフランス製の制御回路ユニットに発展途上国で作られた部品が入っていないとも考えられません。生産拠点のグローバル化が今回のような思わぬアクシデントへつながる原因となっているような気がします。
話は違いますが、先週、我が家のダイニングのTVをある国内メーカのTVに買い換えましたが、BSが映ったり映らなかったりと初日からトラブル発生。修理にきてもらって基板を替えると完治しました。日本メーカ製といえども、聞けば液晶パネルは韓国、基板と組み立ては中国とか。こういうものも日本製品と言えるのでしょうか。
いずれにせよ、県内関係企業のためにも、787の一日も早い原因解明と運航再開、さらには新規機体の納入再開を期待しています。
正月も一週間も過ぎると、すっかり正月気分も無くなり、すでに通常モードになっているところですが、元旦にいただいたあるOBからの年賀状をきっかけに、支援機関のあり方について考えさせられるところがありましたので、書かせていただきます。
その方の年賀状のひと言に「最近、新聞を騒がせませんが、工技総研は大丈夫ですか?」とありました。工技総研関係の新聞記事が少なくなったというご指摘と思いますが、その真偽はともかく、支援機関の評価がマスコミに出る回数で左右されると思うと、いささか寂しいというか、残念という印象を持ってしまいました。自画自賛的になってしまいますが、年末には多くの企業の経営者の方々がわざわざ当方へお見えになり、お礼の言葉を言ってくださいました。当所は補助金や助成金を出しているわけでも無く、むしろ手数料や受託費をいただいて仕事をしている訳ですので、純粋にお礼の言葉と理解し、当方としては、担当した職員の労に感謝するとともに、きちんと研究所が企業への支援をしているという自負と、顧客満足・顧客感動に向け職員が努力してくれている変化を少なからず感じておりました。こうした個々の企業支援成果はマスコミ沙汰になる様な大きなことでもありませんし、「顧客満足、顧客感動」を目標に研究所運営を進めている者として、それで良いとも思っておりました。
しかし、外から見たとき、当研究所の活動はマスコミなどから知ることしかできないわけで、年賀状を書かれたOBのひと言は、一般県民の感想でもあるわけです。
支援機関は「黒子に徹する」が私の口癖で、決して派手に表舞台に出ることでは無く、企業から感謝され、その企業の業績を伸ばす手助けをすることが「支援機関」の役割と思っておりましたが、今回のことでPRとしての情報発信の必要性も感じた次第です。
情報発信としてはマスコミだけで無く、ホームページでの手段もあるわけで、今後はホームページを通じて、支援成果や活動成果を積極的に進めて行きたいと思います。
ただ、支援機関のあり方として、「マスコミを騒がせる」様な事業をすることが目的ではありませんので、本末転倒することが無いよう注意が必要です。ややもすると、そちらが目的になって「行政主導の企業ニーズ無しの事業」へと走りかねません。支援機関は、あくまで「黒子」で良いというスタンスで、企業に役立つ支援事業を行う姿勢を変えてはいけないと思っています。
今年も、皆様からのご利用をお待ちしております。
顧客満足、顧客感動に向け、職員一同全力で支援をさせていただきます。
この国(淡路島程度の面積)が、工業や金融都市、観光都市として発展しており、ものすごい観光客で溢れている様子を見ると、国の施策が明確に解ります。国土や資源が無ければ、何で国民を食べさせて行くか、本気で取り組んだ政治家リー・クワンユ前首相の指導力とその意思を継ぐ現政権(一党独裁の批判もあるが)の力量に脱帽です。
日本も資源が乏しく国土が狭い点はシンガポールと似ており、エネルギー資源のほとんどと食料の約6割は、外貨を稼いで買わなくては国民が生きてはいけません。今度の自民党政権が、どのような経済発展ビジョンを持ち実行できるか、訪問をきっかけにシンガポールと比較してしまいます。
ただ、日本はシンガポールの様な路線を選ぶ必要も無いし、そうあるべきでは無いとも感じています。確かに見た目は非常に発展しているけれども、ソフト面は25年前より劣ってきた感じがし、ホスピタリティ面など人材教育が追いついていない状況でした。
日本が海外にアピールすべきは、シンガポールのようなハード面では無く、ソフト面でさらなる発展をすべきと思います。今、クールジャパンが海外ではブームになっています。観光面なら、「おもてなし」の心や、新鮮な素材を生かした健康的な日本料理、そして清潔で安全な街や自然では無いでしょうか。工業製品であれば、価格勝負の製品では無く、日本人の細やかさを生かした高品質で好感触の製品だろうと思います。そのためには、価格競争の世界から決別し、高くても売れる様な商品開発やブランド戦略を進める必要があると思います。
まだ2回目のブログで今年の最後になりましたが、来年も続けます。
皆様、良いお年をお迎えください。
12年間、庁舎の清掃を担当してくださっていたビル管理会社の女性が今日、退職されました。
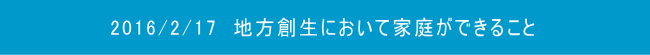
前回、「地方創生」とは「地方の人口減少」が根底にあると書いた。
そして、地方の人口減少を食い止めることに関して国が行えることは各種の制度や補助金などの支援策であり、実行主体は地方自治体や地方大学、地域、あるいは個々の家庭であるとも書いた。そこで、人口減対策には産業活性化が重要であり、そのためには優秀な人材を地域に残すことが必要で、県内の企業へ大学生を連れて巡る「新潟の成長産業体験ツアー(通称バスツアー)」を行っていることを紹介した。
前回ブログの最後に、次回は、「地方創生において家庭ができること」(出生率アップの話ではない)を書くと明言したので、そろそろ(かなり遅いが)書かなくてはならないリミットとなってきた(3月末で退職なので....)。
地方創生すなわち人口減対策で、家庭でできることと言って思い浮かぶのは、単純には出生率のアップであろうが、その課題に関する対策は国も含め各自治体で子育て支援をいろいろ考えているし、当方があれこれ言う立場にはない。
なお、産業支援の立場の人間が人口減対策において「家庭のこと」に言及するのは少々場違いなので、今回は「一家庭人」としての立場で持論と経験談を書きたいと思う。
先の成長産業体験ツアー(バスツアー)の企画段階でも話題になったのだが、学生が就職を決める際に誰からの言葉に一番影響を受けると皆さんは思われるであろうか。「先輩?」、「就職担当の先生?」、「口コミ?」.....などいろいろ意見があったが、どうやら最も影響のある人物は「親」特に「母親」らしいのである(あくまで、らしい)。二十歳過ぎの大人が母親の意見にしたがうの?といぶかる方も多いと思うが、ちょっと自らの若いころのことを思い出してほしい。「〇〇会社を受けようと思う」と親に告げたとしよう、お母さんの第一声は、「そんな会社知らないわよ。もっと有名な会社を受けなさいよ。」(多少言い方は違うだろうが)ではなかっただろうか。知っている会社なら「いいじゃない。大きいとこだし安心ね。」となったはずである。たとえ、お父さんが、「ああ、あそこか。いいんじゃないか」と言ったとしても、お母さんが知らない会社なら、「お父さんはいいの!黙ってらっしゃい。」とTV番組の様な光景が少なからずあったはずである(我が家だけか?)。
最近は私らの時代よりずっと少子化(一人っ子も多い)であるわけであるから、母親の発言はいっそう迫力を増しているかもしれない。
いずれにせよ、親の意見には従わないように見えながらも、冷や酒のように後から効いてくるようである。
というわけで、地元大学の学生さんに地元(新潟出身)に残ってもらうには、あるいは首都圏の大学から地元に戻ってもらうには、親御さんにも新潟の優良な企業を知ってもらわなくてはならないのである。そこで、成長産業体験ツアーは次の段階として、親御さんの県内企業視察も念頭に入れている。
ということで、「地方創生(人口減対策)で家庭できること」とは、親御さんが大企業ばかりに関心を持たず、地域の優良な企業を知り、子供さんたちに勧めていただくことなのである。
私の住む地域の会合で、就職期の子供を持つお父さんに「お宅のお子さんはどこに就職させたいの?」と聞くと、大抵は、「子供を縛っても悪いから、好きなところへ行っていいよと言っている。」と返ってくる。話の取り方によれば「ものかわりのいい親」にも思えるが、私に言わせれば、「子供は親の期待に沿おうとしているもの、親としての希望はちゃんと伝えるべき。」なのである。
ちなみに、私事ではあるが、私には子供(男)が二人おり、二人とも地元大学を卒業し、地元に就職している。小さい時から、「高校はあそこに行ってほしいな」、大学は「県内大学以外はダメよ」、就職も「県内できれば家に近いところね」と、常にこちらの希望を発信してきた。運よくか(人に言わせれば)洗脳か?わからないが、今のところ希望通りになっている。子供の可能性を親が摘んでいのかという意見も聞こえそうであるが、要は皆が幸せなら(と、思いたい)良いのである。
というわけで、早い話、私は早いうちから地域の人口減対策に貢献してきた(それどころか他県から息子の嫁さんをもらったので県民が一名増加した)。ちなみに、当家は家内より私の発言力が強い(つもり)と自負している。
でも正直、息子たちを地元に残したがった本当の理由はお察しのとおり「地域貢献」でも「人口減対策」でもない。というか、そもそも当時にそんな高尚な理念も持ち合わせていなかった。
本当の理由は、至って簡単。息子たちの子供(すなわち孫)の養育と自分たちの老後を考えてのことである。私たち夫婦は共働きなので、息子たちは私の両親(すなわちジジ、ババ)に昼間は面倒を見てもらった。そのために、実家(長岡)の近く家を建て、私は新潟の職場まで通い続けたのである。そして次は息子たちの子供を面倒見るのが、私ら夫婦の任務と思っている。いや、任務というより本音は「孫の面倒を見たーい!」といっても過言ではない。私が目指すは最強の「育ジイ」である(何が最強かはわからないが(汗))。
親御さんが「新潟に残ってほしいなぁ」とちょっと本音をつぶやくことが、少なくても人口流出の歯止めにならないだろうか。ものわかりのいい親から「素の親」になってはいかがだろう。私は日本の昔の家族形態は子育てという面で理にかなっていると思う。でも同居で無くてももよい。次世代に渡って子育てを回していければ良いのである。そのためには、地域における優秀な若い世代の働き場所の確保(すなわち産業の活性化)が行政の大きな課題でもある。
<バックナンバー>
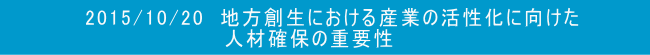
第三次安倍改造内閣が10月7日発足した。第二次安倍内閣の時から「地方創生」が重要課題となり、当時、石破氏が「地方創生担当大臣」に起用されたのはまだ記憶に新しいところだ。
さて、「地方創生」とは、そもそもなんなのか。そんなのは知っているわとの声が聞こえそうではあるが、ここはあえておさらいの意味も込めて調べてみると、実は明確な地方創生の定義は無いようである。「地域の活性化」「地域の振興」という幅広い意味合いで使われており、その施策も「農業」「観光」「科学技術のイノベーション」など、多岐にわたる。わかりやすい言葉では「まち・ひと・しごと創生」とも表現している。
そもそも、「地方創生」が安倍内閣によって提唱された背景には「地方の人口減少」にある。少子化のなかで首都圏への人口集中による地方の過疎化を食い止め、地方の自発的かつ自立的な活性化を促すことが最終目的ということだ。
では、地方の人口減少を食い止める「地方創生」には、何が必要か、何をしなくてはならないかということであるが、政府のできることは農業を含めた地方の産業活性化のための補助金や、公共事業助成、各種法整備という後方支援である。実際に行動に移して「人口流出を食い止める」のは、地方自治体や大学、地域、あるいは個々の家庭の役割である。
地方の人口減は県・市町村にとっては最重要課題で、様々な対策(雇用の創出や若者の創業支援・定住支援など)を行っているが、ここにきて大学にも大きな動きがある。文部科学省は大学の大改革を行おうとしている。国立大学を、1)卓越した教育研究 2)専門分野に優れた教育研究 3)地域貢献 の三つのタイプに分け、個々の大学の使命・役割を再定義しようというものである。県内には国立系大学は三校あるが、そのうち二校は理工系大学あるいは理工系学部を有している。こうした地方の理工系大学(学部)には「地域貢献」が強く求められている。ここで言う理工系大学の「地域貢献」とは、たやすく言えば「地方の大学は卒業生を都会に就職させずに、地域企業に就職させ、産業の活性化と人口流出の減少へ貢献せよ」も意味している。そして、さらには「地方の企業へ大学の研究成果を移転して、新たな産業・事業創出、そしてベンチャー企業の創出に貢献せよ」とも言っていると解釈できる。
今、企業、大学、工技総研は「産学官」で連携し、県内の企業へバスで学生を連れて回る「新潟の成長産業体験ツアー」を実施している。そもそものきっかけはある企業へ訪問した際にその会社の就職担当の方から、「なかなか学生が受けに来てくれない。特に国立大学からは...」という相談を受けたのがきっかけである。「頼まれたら断らない」を信条としている当方としては、すぐに新潟大学工学部の知り合いの先生(大学院の恩師でもある)に相談した。上記の大学の事情もあってか、先生からはすぐに「学生の企業見学会をやりましょう」というお返事をいただいた。そもそも卒業生が県内企業に就職しないのは、県内に優良な企業があることすら知らないからだという共通認識ができ、相談のあった企業担当者と大学、工技総研が打ち合わせを重ね「有意義な工場見学会」となる様、様々な工夫をした。昨年の12月に1回目(2社)を実施し、その新聞記事を見た他の企業の社長から「ぜひうちにも」と頼まれて、2回目、3回目と訪問企業を増やしていった。ちょうど学生も就職を意識する時期であったので、10人限定のバスツアーは有意義なものとなった。学生へのアンケートを見ると、全員が「また機会があったら参加したい」と上々の反応である。「新潟の企業に関心を持つようになった」「新潟県内にこんな素晴らしい企業があるとは知らなかった」というコメントもあり、予算も無しに始めた(企業に負担いただいた)事業としては、上出来である。
「地方創生」は「産業の活性化」無くしてあり得ない。そして産業の活性化は「優秀な人材確保」なくしてはありえない。だからこそ、県内大学を卒業した優秀な学生を地元へ就職してもらう「きっかけ作り」が重要である。就労人口対策、人口減対策は直接的には当研究所の業務ではないが、「産業の活性化」は当所のミッションである。それがゆえ、当方は全力で取り組んでいる。なお、予算化した事業では無いので、今のところ当所では相談を受けた「所長担当」の事業である。先の相談のあった企業の担当者がそれ以降も多大な協力をしてくださっているので続いているといっても過言ではない。
今年も11月から2月までに3回を予定している。一人でも多くの学生が県内企業へ就職してくれることを期待している。
ちなみに、相談のあった先の企業は、今年の採用は良い人材が多く応募してくれたので、もったいなくて予定数を超えて採用したと専務は嬉しそうに語っておられた。これがバスツアーの直接的な効果というのは早急であるが、ツアー受け入れを行った企業担当者のこれまでのやり方やホームページの見せ方などに気づきを与えるという間接的な効果があり、応募増に繋がっているようである。今後は、直接的な効果もが出てくるであろう。
次回(4回目)以降は「工学部主催」から「新潟大学主催」というお墨付きをいただいた。大学改革の中で、新潟大学としてもこの事業に大いに期待していることの表れであろう。
次回は、「地方創生において家庭ができること」(出生率アップの話ではない)を書こうと思う。
またまた、更新が滞ってしまった。もう、言い訳はやめよう。
さて、本題。人はモノを買うとき何が決め手になっているだろう。機能?デザイン?それとも値段?...買うものによって判断基準は違うかもしれない。服ならデザイン優先、電化製品なら機能が優先かもしれない。では、クルマの場合はどうか。最近は、外車がかなり安くなり、街中でも多くの外車を見るようになった。確かにおしゃれなフランス車やイタリヤ車、走りが良いとの評判のドイツ車など人気がある様である。3年半ほど前に、自分の車の買い替え時に、実を言えば外車も検討してしまった。「しまった」と表現したのは、職員には「日本経済の活性化のため日本車を買うべきだ」と飲み会で豪語した手前、検討したことすら恥ずべきことだからである。実際には職員もかなり外車に乗る者が多いので、当方の叫びは単なる「遠吠え」に終わっているが。
で、何を買ったのかというと、国内メーカーの海外生産車なのである。一般に言う「逆輸入車」ではない。「逆輸入車」とは、日本で作って輸出した外国仕様車を日本へ再度輸入するものを指すのであって、国内メーカーが海外で作って日本で売っているものは、日本メーカーの電化製品(ほとんどは中国製)と同じく、「逆輸入品」どころか「輸入品」とも言わない。車にはコンパクトカーですでにそういう車がいくつかある。ほとんどの人はそれを気にしていないというか、知らないで購入している場合もある。で、当方のクルマはイギリス製なのである。ヨーロッパ車の走りの良さに加わり、国内メーカーの品質管理で作られている。走りの良いヨーロッパ車が欲しかった私のニーズに見事に合っていた。
しかし、この車の購入の決め手はクルマ本体ではない。実は担当した営業マンの接客姿勢と豊富な知識が決め手であった。彼は、決して低姿勢でお客に媚びるような接客はしない。また、値引きでつなぎとめようともしない。その代り、こちらの質問(一応、自動車工学を勉強したから専門的な質問もする)に間髪入れず、正確な回答を出す。話していて楽しいのである。結局、展示車も試乗車もないカタログだけで購入を決めた。しかも他の販売店から見積もりも取らず、1回の見積もり額で即決である(太っ腹?)。ある意味、顔も見ず、会ったこともない人と見合い写真で結婚を決めたようなものである。
彼は、購入後のフォローも完璧である。やはりヨーロッパ車。国内メーカーと言いながらも、細かな不具合は結構出た。しかし、そのたびにこちらの不満を解消しようと努力してくれた。結局は治らない(運転席周りのビビり音)もあるが、かなり何度もばらしては見てくれたので、努力に満足している。
3月には家内のクルマを購入することになったが、家内曰く、「○○さんから買える車なら何でもいい」なのである。家内も彼のファンである。
人はモノを買うときに、様々な優先項目がある。クルマなら多くの場合は、車のタイプと予算をもとにいくつかのメーカーのクルマを比較して買うのが普通と思う。昔は自分もそうであった。クルマ本体や価格より「営業マン」で購入を決める。そうさせる営業マンはすごい。クルマに限らず、人はモノを買うとき、機能やデザインも重要だが、実は「満足感」が一番重要なのである。それが「営業マン」であるなら、「サービス精神」の神髄がそこにある。
ちょっと変な表題であるが、仕事とは言われたことをするだけで無く、自ら仕事を見つけることで、より質の高い成果を生むということを書きたいのである。
多くの仕事は、すでに決まった分掌や、上司からの指示で行う仕事がほとんどである。しかし、書類一つを作るにも、言われたこと以外に「この資料を用意すればよりわかりやすいな」とか、「指示の内容より、この内容の方が良いから提案してみよう」などと、工夫して仕事をしてくれる人がいる。こういう人が、私の思う「出来る人」なのである。言われたことしかしない人、さらには言われたこともきちんと出来ないヒトは「人に役立つ仕事」というところからはほど遠く、且つ、自分自身も満足感を得られていないヒトだと思う。「出来る人」というのは、「人の役に立とうとして行った仕事ぶりの結果」として生まれる評価だ。
本当かどうかはわからないが、ある記事によれば、会社には2割の出来る人、6割の普通の人、2割の仕事の出来ない人で成り立っているそうである。「収益」が判断材料になる企業においては、2割の出来る人が、2割の出来ない人を養っているということになってしまう(6割はそれなりに自分の分は稼いでいるということか)。さて、公務員の場合はというと・・・・「収益」という評価は無いから、書き様が無いので止めておく。
当研究所に話を移す。当所には大きく二つの職種に分けられる職員がいる。そう、研究職(技術職)と一般職(事務職)である。そして、一般職には、正規職員と臨時的職員(産休、病休の補充職員など)の方、そして非常勤職員(一般的に言えばアルバイト職員)の方がいる。研究職にも臨時職員もいるが、今日は事務職の非常勤職員の話である。
今年、7月に非常勤職員の一人が、新たに採用した方に替わった。この方の仕事としては、試験成績書の郵送作業や回覧文書の整理、郵便物の収受、庶務用品の購入など、いろいろな庶務関係の仕事を手伝ってもらっている。職員が業務を円滑に進めるための、サポート役である。
非常勤職員はフルタイム勤務では無いこともあり、まだ子育て世代の女性の方々の応募が多い。結婚されいったん職を離れたが、子育てに慣れてきたので家事に影響無い範囲で働きたいという方の応募が多いようである。こうした方々は独身時代にはそれなりのキャリアを積んだ方も多く、また家事や育児と仕事を両立してやりたいという意欲のある方々であるから、当然、応募者の多くは能力の高い人になる。前任者も優秀な女性で、細かな事にも気を遣ってくれ大変助かっていた。しかし、能力があるということは、こちらがお願いする仕事の内容では役不足*という心配もある。
(*誤用が多いが、正しくは「人」対して「役(仕事)」の方が不足しているという意味)
このたび新たに採用になった方も、能力・意欲が高い人である。先日も、私が講演で使う資料のグラフ作りをお願いしたが、期待以上に早く、且つこちらのイメージを的確に表したグラフを作ってくれた。ますます、役不足が心配になってしまった。でも、彼女はそんな事はおくびにも出さず、与えられた仕事を黙々とこなしている。そして、さらに感心するのが、自分で仕事を見つけて、実行していることである。彼女は、自分の能力をひけらかすこともなく職員のサポート役という立場を認識し、何をしたら職員の役に立つのかに気を配っている。まさに私の言う「出来る人」なのである。
 例を挙げたらきりが無いし、気づかずにいるものがいっぱいあるのだが、ある日、ラベルライターを使おうと思ったら、テープの幅や色がわかる様、綺麗に並べられていた(写真)。すぐに必要なテープを見つけられた事は言うまでも無い。
例を挙げたらきりが無いし、気づかずにいるものがいっぱいあるのだが、ある日、ラベルライターを使おうと思ったら、テープの幅や色がわかる様、綺麗に並べられていた(写真)。すぐに必要なテープを見つけられた事は言うまでも無い。「出来る人」は、常に誰かの役に立つことを考えている。「出来る公務員」は常に納税者である県民や企業の役に立つことを考えていなくてはならない。
先のブログでも書いたように、私は遠距離通勤者で通勤に要する時間も長い。なので、若いときから出来るだけ終業時間までに仕事が終わる様、いくつかの仕事をパラレルで進めたり、効率を高めるために実験道具や工具の整理整頓をしたり、自分なりの工夫をしてきた(ちなみに、この習慣が料理作りの段取りにも役立っている)。整理整頓は、今や工技総研の毎月の「5S活動」に繋がり、外部の方やOBの方からもずいぶん研究室が綺麗になったとお褒めの言葉をいただくこともある。
そもそも整理好きのこともあり、そして家内が仕事を持っていることから、忙しい家内に代わり私生活でも自然に「掃除」はほとんど私の担当のようになってきた。毎日は出来ないので、土曜日の午前中はトイレも含め徹底してやった。家内は、土曜や日曜も出勤、ウィークディも帰りが私より遅いことも非常に多かった。そんなわけで、掃除のみならず夕食を作ったり、子供の世話や、洗濯なども当然のようにやって来た。子供が大きくなってからは、「出来る者が、出来る時に、出来る事をする」が我が家の暗黙のルールになり、各自が出来る家の仕事をするようになった。夕飯も早く帰った者が作る。今でも家内が遅くなる(週に1~3日)ときは、私や同居している次男も台所に立つ。
そもそも、私は昔から「これは女の仕事」「これは男の仕事」という意識が無い。まして、「夕飯作りやトイレ掃除は女の仕事」というような差別的な意識も無い。だから、男は外で働いているのだから、家に帰ったら何もしないという人の感覚はわからない。奥さんが専業主婦ならいざ知らず、共働きならするのが当然である。共働きなのに、家のことは何もしない男の人は、私にとっては異星人だ(笑)。そういう人は、「オレは女房より大変な仕事をしている」とでも言いたいのであろうか。しかし、会社で仕事が「出来る人」は、「家庭の仕事もきちんとこなす」というのが私の持論だ(私が「出来る人」かは別として(汗))。
さて、ちょっと話を戻す。私にとって、仕事も、家事も、トイレ掃除も同じ意識で「自分なりに」一生懸命する。なぜなら、仕事も家事も含め誰かの役に立つという点で同じだからである。トイレ掃除は、人によっては「負の作業」のイメージを持つひともいるようだ。しかし、綺麗なトイレは、皆が気持ちよい。だから、使う人のことを考えながら行うトイレ掃除は楽しい。職業に貴賤が無いように、家事仕事にも貴賤は無い。
話は変わるが、東京ディズニーランドのリピータはとても多い。聞くところによれば、ハード面だけで無く、スタッフの一生懸命に楽しんでもらおうとする姿勢によるところが大きい様である。そして、実は隠れた理由がもう一つある。「カストーディアルキャスト」と呼ばれる、主に清掃担当を行うスタッフの仕事ぶりと笑顔なのだそうだ。彼ら、彼女らはトイレ掃除にも「誇り持って」取り組んでいる。仕事でやっているだけと言えば、それまでだが、彼らには「使う人のため」という共通の思いがある。
またまた、ブログの更新が滞ってしまった。文章を書くときはまとまった時間が取れないとなかなか手に付かず、お盆は来客も無く更新できるかと思ったら、県庁からの宿題などに費やされ、結局今日になってしまった。今日から9月、もう秋である。
私は自宅が長岡市内にあるので、バスと新幹線、そして徒歩といろいろな交通手段を使いながら、待ち時間を含め片道1時間40分くらい掛けて通勤をしている。東京なら、郊外からその程度の時間を使って通勤する人は多いようであるが、新潟でこれだけ通勤時間を掛ける人はそう多くはいないと思う。我ながら良く通っていると思うが、歳のせいか、若い頃に比べると長距離通勤も疲れる様になってしまった。あと約1年半がんばらねば。
さて、今回の話は通勤時間の長いことをぼやくのが趣旨ではない。これだけ長い通勤をしていると、じつに様々な不快な場面に遭遇することがある。満員なのにバスの二人掛け席を一人で占領するヒト、新幹線エスカレータでの「歩行禁止注意」を無視して人にぶつかりながら降りていくヒト、歩道の真ん中を傍若無人に疾走する自転車に乗るヒト、などなどマナーを知らないヒトの例を挙げたらきりが無い。しかもほとんどが若者である。
日本人の規律正しい姿勢や人を思いやる利他的行動について、日本に来た外国人が賞賛するテレビ番組を最近見た。確かにほとんどの人は車が来なくても赤信号を守るし、新幹線ホームで列に割り込む人はまずいない。よほど、外国ではそうした決まりを守らない人が多いのか、日本人はとても規律正しく、民度が高い国民と思われているようだ。子供の頃を思い出すと、バスを待つ列も曖昧だったし、割り込みも良くある光景だった様に記憶する。日本人がきちんと列をつくり割り込まなくなったのも、道路で赤信号を守るようになったのも、ここ数十年のことのように思う。「衣食足りて礼節を知る」ということわざがあるが、日本が海外から賞賛される民度を身につけたのも、まさに日本人みんなが豊かになってからのことでは無いだろうか(飽食の時代とまで言われた)。
しかし、最近はグローバル化の影響で、近年は日本国民の貧富の格差が広がっている。特に問題なのが若者の貧困である。先の「マナーを知らない」行動をするヒトの多くは若者であった。彼らは富める親に育てられ、その生活がずーと続くと思い込んだまま大人になってしまった。勉強しなくても何かの仕事に就けて、親と同じくらいの収入があって、親と同じくらいの生活ができると思っていたはずだ。その頃、彼らには危機感は無かった。しかし、急速なグローバル化が進み、国内の製造業の中でだれでも出来る仕事は海外に流れ、知識や技能をさほど必要としない仕事は日本には残っていない。すなわち、ただ単にみんなが高校に行くから自分も進学し、目的も無く勉強もしなかった人のできる仕事は無くなってしまった。ある意味、学生の時にがんばった人しか豊かな生活を送るチャンスを得られない時代に突入した。
そうすると、これから問題になるのが「貧困の悪循環」である。親の収入の低い世帯の子供の進学率は富める世帯に比べ圧倒的に低いという調査データがある。その中には優秀であっても進学出来ない子供が含まれている。政府もようやくこの問題の解決に向け検討を始めている。人材(人財)こそが日本の資源なのだから大いにやって欲しいと思う。是非とも優秀な人材には手厚い支援をして欲しいと思う。そして、進学する側も認識をきちんともって欲しい。「大学に入ること」が目的では無い。「大学で知識を得ること」が目的なのだ。勉強するのは「良い点を取る」ためでは無く、「いい学校に行く」ためでも無い。知識を得ることで「仕事へのチャンス」を広げることである。すなわち「勉強」は「食っていくため」にするのである。自分で食っていけない人に「人のために生きる」ことは出来ない。親や学校はそのことをきちんと教えるべきだ。
話は、だいぶずれてしまった。前述の「無礼」な若者がすべて「貧困な子供」とは言わない。しかし、低所得世帯の子供の進学率が上がり、そこできちんと勉強し、豊富な知識を身につけ、そして人に役立つ仕事に従事し、豊かな生活を送れるようになって、この国に貧困の格差が無くなれば、満員のバスで席を占領する不届き者や、ぶつかりそうに歩道を疾走する自転車乗りも、すこしは少なくなるのではないかと密かに期待をしている。「衣食足りて礼節を知る」ということわざは、「管子」という人の故事から来ているそうである。欧米でもMeat and cloth makes the man.とかWell fed, well bred.ということわざがあるそうだ。衣食を心配しているようでは、他人への気配りなどできなというのは、万国共通の認識のようである。
1/24 「サービス精神」と「お・も・て・な・し」
年末は予算、人事などいろいろなことが重なり、またまたブログの更新の間が空いてしまった。ブログなのだから気軽に書いてアップしてもいいのだが、皆さんの目に触れると思うとそう簡単でも無いのである。(と、まずは言い訳)さて、当所は技術の面で企業の皆様へサービスを提供する行政サービス機関である。職員にも「サービス精神の向上」を説き、「顧客満足」「顧客感動」に繋がる業務をしてもらうように機会があるごとに訓示している。かなり対応は良くなって来ていると自負するが、個々の職員による接遇や対応姿勢にバラツキがまだあるのは否定できない。
今、CSアンケート(顧客満足度アンケート)を、昨年利用していただいた企業様へ郵送し回答をいただいているところであるが、すでに中には対応姿勢にご不満をもたれた企業様の回答があり、管理職として大きく反省をするとともに、お詫びの気持ちで一杯だ。せっかくいただいたアンケートのご意見なので、改善に向け必ず対応をすることをお約束する。それは、優れた対応をしているほかの多くの職員のためにでもある。
ところで、東京五輪の誘致活動での滝川クリステルさんのプレゼンにより昨年の流行語大賞にもなった「おもてなし」は、当方が職員に言っている「サービス精神」と何が違うのか疑問に思い、Webで調べてみたらこんな記述があった。
○おもてなし:ホスピタリティのこと。病院(Hospital)を語源とし、対価を求めない自然発生的な対応。
○サービス:ラテン語の奴隷(Servitus)を語源とし、上下関係がはっきりした場面で用いる。このためホテルでサービスを受ければ、サービスチャージやチップなど対価が発生する。
「おもてなし」の記述は、日本人の持つ「人のために役に立つ」という利他的志向が根底にあり、「対価を求めない自然発生的」というのは、何となく理解ができるが、「サービス」の記述は、必ずしもわれわれ日本人が捕らえている言葉のイメージと完全に一致しているとは思えない。日本では「サービス」という場合も、ほとんど「おもてなし」に近い意味でとらえているように思われ、上記の記述は少し語源にこだわっているようだ。ただ、海外でのサービス(SERVICE)では確かにこの記述が成り立ちそうな場面も多いが、調べると海外でも「奉仕」という意味にも使うようで、やはり上記の記述は現在の「サービス」の意味を完全には記述していないようだ。
ただ、「サービス」と「おもてなし」は、明らかに聞いた時の語感が違う。職員に「企業の方にサービス精神をもって対応してください」と言うより、「企業の方にはおもてなしの心で対応してください」と言うほうが、職員の心に残りそうだ。
どこからか「公務員におもてなしの心なんて無理、無理!」なんて声が聞こえてきそうであるが、そう思われていると思えば思うほど、私の改革意識は高まるのである。来年のCSアンケートでは「不満回答ゼロに」と強く、強く思う。
9/27 職員が一般公開に全力を尽くす訳
先月末の8月24日(土曜日)に「ものづくり広場2013」と銘打って、当研究所の一般公開を行った。毎年、夏休み終わりの最終土曜日にしており、ここ数年は隣接する新潟テクノスクールとの共催である。当所の公開事業としては、産業界(企業)向けの「研究成果発表会(施設見学も含む)」や各種セミナーなどを開催している事から、普段は企業の方が来所されているが、一般の県民の方が来所される機会はほとんどない。そこで、一般公開は当研究所が行っている業務を県民の方にもっと知ってもらうということで、そもそもは始まった行事である。
確かに当研究所のPRも重要であるがのだが、それよりも「県内企業のすばらしい技術」を一般県民の方々にも知ってもらいたいのと、日本の未来を担う子供達に「科学・技術」への関心を持ってもらいたいとの目的で、当所の一般公開も県内技術を活用した「プレス技術の体験」や「プラスチック成形の体験」、「切削技術の実演」などを加え、物作りの楽しさを体験してもらえる内容へと変化させてきた。

日本のもの作りはグローバル化の中で、どんどん海外へと生産拠点が移転している。しかし、資源の無い日本は「工業製品」で外貨を稼いでエネルギーや原料を購入しなくてはならない。食料品だって、国内自給率は40%強しかなく、中国や他の諸国から輸入しているのが現実だ。いかに外貨を稼ぐ産業の発展が重要なのかが解ろうというものである。
前述のように産業構造の中で日本の産業のあり方はどんどん変わって来ている。従来のように品質の良い工業製品(電化製品など)を日本で生産して、海外に輸出するという形態はすでに崩れ、日本メーカといえども、中国やアジア諸国などの人件費の安い国外で作って、日本国内や海外で販売するという形態になっている。車についても最近では消費地である海外生産へと代わって来ている。すなわち、工業製品を国内で作るということ自体が無くなりつつあるということである。ただ、それは大量生産品や、技術が確立し設備とそれなりの作業者がいれば作れる汎用の工業製品であるということに気づくべきである。言い方が悪いが、その製品に「魂」は無い。
日本人には「優れた技能」と「より良いモノを作りたいという向上心」そしてなにより「人に喜んでもらえるものを作りたい」という「利他主義」とも言える国民性が根底にあると個人的には思っている。急成長してはいるが拝金主義の国とはもの作りの姿勢が決定的に違う点だ。
 私たちが直接には産業に関係の無い一般県民の方々を対象とした「一般公開」を行い、特に子供達に「もの作り」の楽しさ、凄さを伝えたいという意味は、そこにある。作る側が楽しくなくては、その製品を手にする人も幸せにはなれない。それは「料理」と全く同じなのだ。
私たちが直接には産業に関係の無い一般県民の方々を対象とした「一般公開」を行い、特に子供達に「もの作り」の楽しさ、凄さを伝えたいという意味は、そこにある。作る側が楽しくなくては、その製品を手にする人も幸せにはなれない。それは「料理」と全く同じなのだ。廊下ですれ違ったあの幼い子が、走って会場へ向かって行ったあの子が、二十年後、きっと日本の産業を支えている。
8/16 台湾茶を知ろう!
ブログの更新にかなり間が空いてしまった。お盆休みで時間がとれる間に更新だ。さて、7月末からちょっと早い夏休みを取り、恒例の海外旅行へと行ってきた。どこにしようかと迷ったあげく、三年連続の「台湾」である。プチ海外旅行としては中国、韓国も関心が無いわけでは無いが、近年のますます反日感情が強くなっている所へ行く勇気もなく、再度、親日的で食べ物もおいしい台湾となった。台湾に行く理由は2つある。一つは「小籠包」に代表される中華料理(台湾料理)と、もう一つは、日本では一般に烏龍茶と言われている「台湾茶」の購入である。
烏龍茶は日本ではペットボトルで売られている「茶色のお茶」がなじみ深いが、その原材料の茶葉産地を見ると中国産であることが多い。確かに烏龍茶の茶樹は中国が原産であるが、中国から台湾に持ちこまれ、その後、日本統治時代の茶葉振興施策により品種改良(台湾の研究機関の功績が大きいとのこと)がなされ、今では中国烏龍茶とは全く違うと言って良いほどのお茶となっている(色も薄黄色から茶色まで様々)。どうやら中華料理も同様のようで、近年は日本やシンガポールにも支店を出している小籠包の「ある有名店」は中国本土からの観光客がいっぱいだ。本土より旨いということだと想像する。余談になるが、この小籠包の有名店は、最初に台湾へ行った10年くらい前は日本人観光客がいっぱいで、店員も日本語で対応してくれていたが、最近は中国人観光客の方が多くなったせいか、日本語の話せる店員も限られているようだ。去年、若い女性の店員が、こちらが日本人とわかるととてもうれしそうに対応してくれたことが印象に残る。すなわち、年代を問わず親日的だ。
台湾茶の話に戻そう。戦後は栽培技術、焙煎技術の改良・機械化により安定した品質の良い台湾茶が全土で広く手に入るようになった。日本ではまだ本格的な台湾茶が買える店が少なく(県内では新潟市に一軒ある)、ネット通販などでも買えるものの、良いお茶を買うなら絶対に現地へ行くしか無いと思っている。
台湾茶は半発酵茶(日本茶は無発酵茶、紅茶は完全発酵茶)で、発酵の少ないものからかなり進んだものまであり、台湾茶にはその発酵段階や茶樹、茶葉の取れた山・高度によって多くの種類が存在する。私のお気に入りは、「高山烏龍茶」や「阿里山金萱茶」「文山包種茶」などだ。阿里山金萱茶はほんのかすかなバニラの香りがするが、通販などで買うと香料を使ったモノがあるので、そういう意味でも現地購入が安心だ(ただし、現地でも香料を入れている店もある)。出来れば、「工夫茶器」を使って香りを楽しむ飲み方をして欲しい。
 実は私たちは今まで六回も台湾に行っている。そしていつも同じ店で購入している。茶葉農家から始まり焙煎工場も持っている家族経営の店で、そういう意味でも安心だ。店に行くと相手をしてくれるのは次男の呉榮峻さん。少したどたどしいながらも日本語が話せる。またそのお嫁さんがこれまたかわいい美人だ(当然、画像の左)。日本語は奥さんの方がうまいかもしれない。この店からは今はホームページでも購入出来る。
実は私たちは今まで六回も台湾に行っている。そしていつも同じ店で購入している。茶葉農家から始まり焙煎工場も持っている家族経営の店で、そういう意味でも安心だ。店に行くと相手をしてくれるのは次男の呉榮峻さん。少したどたどしいながらも日本語が話せる。またそのお嫁さんがこれまたかわいい美人だ(当然、画像の左)。日本語は奥さんの方がうまいかもしれない。この店からは今はホームページでも購入出来る。先に書いたように、日本に統治されていたにもかかわらず台湾の人々は年齢を問わず非常に親日的で、日本へ行くことにあこがれる台湾の若者も大変多いようだ。
 実は、日本と台湾は正式な国交は無い。人口もわずか約2,300万人と少ない。なのに、東日本大震災の時に日本赤十字社に送られた義援金は最多の米国とほぼ同額の29億円超である。金額で善意を区別すべきでは無いが、人口、GDPを考えたらその善意と日本への思いの大きさに目頭が熱くなる。こんなに親日的で日本を応援してくれている台湾を日本人はどのくらい知っているのだろう。もっともっと知って欲しいと思うのである。「台湾茶を知ろう!」の意味はそこにある。もちろん台湾はお茶や中華料理だけでは無い。有名な「Taipei101」や「淡水」観光など見所もいっぱいなのだ。
実は、日本と台湾は正式な国交は無い。人口もわずか約2,300万人と少ない。なのに、東日本大震災の時に日本赤十字社に送られた義援金は最多の米国とほぼ同額の29億円超である。金額で善意を区別すべきでは無いが、人口、GDPを考えたらその善意と日本への思いの大きさに目頭が熱くなる。こんなに親日的で日本を応援してくれている台湾を日本人はどのくらい知っているのだろう。もっともっと知って欲しいと思うのである。「台湾茶を知ろう!」の意味はそこにある。もちろん台湾はお茶や中華料理だけでは無い。有名な「Taipei101」や「淡水」観光など見所もいっぱいなのだ。(画像は淡水の「情人橋」(バレンタインディに開通したことから別名:恋人橋)よりの夕日)
6/11 捨てたのは「良心」
夏になろうというのに春の話であるが、4月の終わりの日曜日の早朝に町内のクリーン作戦があった。町内住民のボランティア参加が原則なので、町民全員が参加している訳では無いが、それでもほとんどの町民が早朝から道路脇のゴミや缶を拾って回った。クリーン作戦を始めた十年ほど前?に比べると毎年ゴミが少なくなっていき、いままでは自分だけでもスーパーのポリ袋で2,3個にはなっていたのが、今回は行程の八割過ぎても私の袋は1個がいっぱいにならないでいた。クリーン作戦を各地で行っているゆえの意識の変化なのだなと思いながらゴミを探していた。なかなか見つからないゴミが、ある地点からいきなり急増する。缶はもとより、コンビニで買って食べた容器の残骸、果ては赤ちゃんのおむつが風雨で分散したと思われる綿状の塊........。唖然として言葉も出ない。
私の住居は越後国営丘陵公園に近い町にあり、この道路は国営公園から来た道が国道に上がるためのインターチェンジのようなカーブになる。カーブの遠心力を利用して藪にゴミを捨てるというわけだ。時々、藪に入らず路面に転がっていることもある。見えるゴミは、ときどき地元の産廃処理会社の社長が拾ってくださっていると聞く。
東日本大震災では日本人の秩序の良さ、マナーの良さをたたえる外国メディアが多かった。日本人の民度の高さに世界中が驚嘆した。日本を訪れた外国人のブログでも、日本はゴミが少なく清潔なことを賞賛する記述が多い。しかし現実は....。
ゴミを捨てているのが日本人か外国人かは解らない。しかし、言えることは一つ。たばこの吸い殻と同様に捨てたのはゴミだけでは無い。その人の「良心」もなのだ。シンガポールの様に「ゴミのポイ捨て、即罰金」にしないと、ポイ捨てが無くならない国になってしまったのだろうか。
クリーン作戦から一ヶ月、すでに多くの「誰かの良心」が捨てられている。
5/7 ハバロフスク出張
年度はじめは、いろいろな総会出席、講演などにお呼びいただき、その準備などでなかなかブログの更新も出来ないでいた(と言い訳がましいが)。ハバロフスク出張準備もその理由の一つだが、ようやく帰国して一息ついたのでハバロフスク出張をテーマにブログの更新をすることにした。出張の主目的は「県内企業の航空機産業」と「植物工場装置」のPRである。成果としては、航空機だけに限らず、機械など工業製品全般にわたる「工業ビジネス研究会(交流会)」のようなものを、両地域の企業で立ち上げ、お互いの情報交換をしながら、新潟の工業製品や部品をロシア側へ供給するビジネスを検討することとなった。また、植物工場については、PRした食品会社の関係者ら(約20名)は大いに関心がありそうで、何人かは新潟まで来て現在実証試験中のキャビネット型植物工場や、地中熱・雪冷熱利用で実証試験中のコンテナ式植物工場を視察したい様な話もでた。
いずれも今後の展開を期待したい。
さて、ハバロフスク出張は十数年前に行って以来の久しぶりであるが、なんと泊まったホテルは同じインツーリストホテルであった。町の風景といい、ホテルの内外装といい、一見するだけでは、ほとんど変わった様子が無い。違いと言えば、昔は日本の中古車(しかも店名の入ったままのバン、小型トラック)が多かったが、今はほとんど無く、新車から使っている様な日本車が多かった。ただ、砂塵と泥をつけたままで、ほとんどのクルマが真っ茶色。洗ってもすぐに汚くなるのでまだそのままとのこと。本格的に春になり道路補修と清掃が終わると綺麗にするようだ。確かに、まだ冬(の終わり?)なのかハバロフスクは緑が全くなく、街路樹も公園も茶色のままだ。緑が息吹くと綺麗な街になるとのこと。
滞在した期間の気温は5℃~8℃位で新潟より少し寒い位であったが、たまたま比較的暖かい日が続いただけで、本来は0℃~3℃のようだ。アムール川の氷もまだすべては溶けずに川を覆っていた。1回目のハバロフスク訪問時は時期が12月末だったので、アムール川も凍り付いており、川の上を数十メートル歩いた記憶がある。
ロシアというと旧共産圏のイメージを払拭出来ない方もいる(当方もそうであったが)と思うが、現在のロシアは堅苦しさも無く、外観は変わらないものの内装がおしゃれな飲食店も多い。アムール川岸も昔はアル中のたまり場だったそうだが、今は綺麗に整備され市民の憩いの場になっていた。日本よりスピードが遅い感じはあるが着実に発展している。
ロシアとの関係では領土問題などまだ解決していない課題はあるものの、個人レベルでは親日的である。細かなところでは日本の感覚で期待するとがっかりすることもあるかもしれないが、そこはお国柄と割り切りたい。親日的であるということは、ビジネス面でとらえれば、反日運動・ボイコット運動は起きそうに無く、リスクが小さい。新潟の製品を売って行くには安定した市場ととらえることも出来るのでは無いかと思う。
観光交流、ビジネス交流も含め今後の展開を期待したい。
2/28 「顧客満足」と「顧客感動」
県内の山沿いは3メートルを超える積雪になっているが、新潟市をはじめ私の住居のある長岡市などの平野部は昨年に比べ積雪は今のところ少ない方である。しかし、3月になろうとしているにもかかわらず、朝はまだまだマイナス気温で、通勤にはつらいものがある。さて、当研究所ではこの時期に毎年「CSアンケート」を実施している。直近2年間に当研究所をご利用いただいた事業所様へ送り、返送していただくという形であるが、今年は約1200社にお送りし、現在約36%の企業から回答をいただいている。
現在は集計中であるのでまだ最終の数値ではないが、今年も例年同様に、「職員の対応」としては「満足」「やや満足」を合わせて9割以上になる。依頼試験や機器貸し付けなどサービスごとの満足度の数値もほぼそれぞれ9割近くとなっている。
ただ、ここでこの数値をどう見るかが重要なポイントである。昨年度のアンケート結果では、ある外部の方から「満足度が9割以上とはすばらしい」とおっしゃっていただいた。お褒めの言葉は誠にうれしいし、がんばってくれている職員に感謝したい。しかし、ただそれで満足しているわけにはいかない。研修のお陰もあり、確かに、若い職員をはじめ多くの職員の対応は以前に比べ格段に良くなっており、昔のような「お役所的」な対応は非常に少なくなっていると思う(それでも完全にゼロでは無いが)。接遇面以外の試験業務、技術支援など当所の基本サービスの質も優秀な職員が採用されてきており、かなり上がってきているとも思う。しかし、それでも「やや不満」「不満」は計2%ありゼロでは無い。管理職としては、9割超えの満足度の数値に満足せず、2%のご不満にどう対応するかが重要と思っている。
民間企業も含めどんな分野でも顧客の不満を0%にすることは出来ないかもしれない。たとえミシュランの三つ星レストランでも「不満」という人がゼロでは無いだろう。しかし、ゼロにはならないにしても、ゼロにする努力をする事こそが大切であり、その努力をすることで「不満」はゼロにならなくても、「満足」の評価をしていたお客様がその上の「感動」の評価に変わるものと思う。
「満足」が「対価相応」と解釈すれば、「感動」とは「そこまでしてくれたの!」という驚きである。当所の業務の中での「依頼試験」を例に取ろう。企業から依頼された試験を約束の日までに約束した通りの内容で結果を出せば、企業の「満足」は得られるかもしれない。しかしさらに、「期日より早く終わらせた」、「途中経過の報告をした」、「試験結果の悪かった原因まで調べておいた」などのちょっとした気遣いや対応が加わると「満足」が「感動」に変わるのでは無いだろうか。それができる人は、前回ブログで書いた「ヒトは人のために生きている」という姿勢と繋がる。
サービスの向上は仕組み作りやマニュアル整備だけで達成できるものではない。職員ひとりひとりの意思によって、真の顧客感動を得ることができるものと考えている。
2/1 ヒトは人のために生きている
今日から2月。まだまだ大雪が心配な季節が過ぎたわけでは無いが、今日は晴れて、気温も10度くらいまで上がったようだ。今日、福島県庁へ応援に行っていた職員が2ヶ月ぶりに戻ってきた。被災地での復興のための業務はさぞかし大変だったと思うし、慣れない地での生活も寂しいものがあったと思う。今日は、関係部署職員で彼女の「お疲れ様会」がある。当地の様子をしっかり聞いて、自分なりに出来る東北応援を再度思案してみたいと考えている。
こうした業務を「仕事」と考えれば、人によっては苦痛に感ずる人もいるかもしれない。しかし、「東北のため」「人のため」と考えれば、また違った意欲が生まれる。あるいは、「仕事」と思って赴任しても、仕事をしているうちに「人のため」という感覚に変化することもあるだろう。
「仕事」を何のためにするのかと聞かれて、人はどの様な言葉を返すのであろうか。「生活のため」、「お金のため」などというのは容易に想像がつく。「この仕事が好きだから」、「スキルアップのために」などというのもあるかもしれない。突飛なところでは「暇だから」などと言ううらやましいものもありかもしれない。
しかし、一般的には仕事が無ければ生活が成り立たない人がほとんどのはずであるから、「生活のため」というのは、ほとんどすべての人に当てはまる。要は、それ以外にどんな目的、意識があるかである。企業は利益を上げるのが目的という人がいる。行政はそうした共通の目的が無いから真剣さが足りないという人がいる。でも、そうであろうか。企業であれ、行政であれ、最終的には「人の役に立つため」に仕事をしているのだと思いたい。
企業は利益を挙げるのが目的と言うけれど、最終的に社会(人)に役立たない仕事をしている企業は潰れる。社会(人)の役に立つ商品やサービスを提供するから、結果として利益を生んでいるのだと思う。お金に取り憑かれたヒトや企業は、ますます欲を出し、最後は非社会的な行動で事件沙汰になる事例は枚挙にいとまが無い。そうならなくても、そういう仕事の仕方をしているヒトは、どこまで行っても満足心を得られない。周りから目立つことを目的に仕事をしているヒトも同じだ。
ヒトは人のために行動し、その人からこっそりとでも感謝されたとき、お金にも勝る満足感・達成感を得ることが出来る。そしてそれは、周りの人も自分も幸せになれるということである。それは、個人だけで無く企業であれ、行政であれ同じだ。自分や自分たちの欲望(お金や名誉欲)のために仕事をしていないか、時々振り返ることが大切である。
私は思う、「ヒトは人のために生きている」。
(今回より、随筆調で書きます。ご容赦ください。)
1/24 ボーイング787の一連のトラブルの影響
前回のブログで紹介した様に、年度末にシンガポールへ行ってきましたが、その際に利用した機体は10月からJALのシンガポール線に就航したばかりのピカピカのボーイング787(ドリームライナー)でした。わざわざその機体の運航便を選んで座席を購入(実際はマイレージ特典)しました。航空機に限らず自動車でも「初期故障」というのは新型機には付きものというのは承知していたので少々不安もありましたが、それより噂の787への興味心が優先してあえて乗ることにしました。その旅行後に、燃料漏れトラブルやバッテリートラブルの重大インシデントの発生で787は運航停止、さらには新規納入の見合わせという事態になり、今思えばちょっと危険な目に遭う可能性もあったなと複雑な思いがあります。
さて、運航停止、新規納入停止という事の影響は、単にJALやANAなどの運航会社に影響を及ぼすだけではありません。準日本製と言われるように787の機体の35%は日本の部材や製品が使われています。実は、内装品になりますがギャレイやラバトリー(トイレ)などはユニットで新潟県内の企業が一手に製造しており、さらにその一部を下請けしている企業も多くあります。今回の騒動は決して、航空機メーカ、電池メーカの一大事では済まされません。3年遅れでようやく就航し、これから本格生産という期待が出てきていた時だけに、誠に気に掛かる出来事です。
アクシデントの中でも一番の重大事がバッテリー火災で、その製造元が日本メーカということで、原因次第では、787を準日本製とアピールしていたのが裏目に出る可能性もありますが、バッテリーはフランスのメーカへ納入され、電源制御回路はそこで組み込まれており、バッテリーだけの問題では無いのではないかと思って(期待して?)います。さらには、日本製品と言われているバッテリーの内部部品やフランス製の制御回路ユニットに発展途上国で作られた部品が入っていないとも考えられません。生産拠点のグローバル化が今回のような思わぬアクシデントへつながる原因となっているような気がします。
話は違いますが、先週、我が家のダイニングのTVをある国内メーカのTVに買い換えましたが、BSが映ったり映らなかったりと初日からトラブル発生。修理にきてもらって基板を替えると完治しました。日本メーカ製といえども、聞けば液晶パネルは韓国、基板と組み立ては中国とか。こういうものも日本製品と言えるのでしょうか。
いずれにせよ、県内関係企業のためにも、787の一日も早い原因解明と運航再開、さらには新規機体の納入再開を期待しています。
1/9 年賀状のひと言に支援機関のあり方について考える
新年明けましておめでとうございます。正月も一週間も過ぎると、すっかり正月気分も無くなり、すでに通常モードになっているところですが、元旦にいただいたあるOBからの年賀状をきっかけに、支援機関のあり方について考えさせられるところがありましたので、書かせていただきます。
その方の年賀状のひと言に「最近、新聞を騒がせませんが、工技総研は大丈夫ですか?」とありました。工技総研関係の新聞記事が少なくなったというご指摘と思いますが、その真偽はともかく、支援機関の評価がマスコミに出る回数で左右されると思うと、いささか寂しいというか、残念という印象を持ってしまいました。自画自賛的になってしまいますが、年末には多くの企業の経営者の方々がわざわざ当方へお見えになり、お礼の言葉を言ってくださいました。当所は補助金や助成金を出しているわけでも無く、むしろ手数料や受託費をいただいて仕事をしている訳ですので、純粋にお礼の言葉と理解し、当方としては、担当した職員の労に感謝するとともに、きちんと研究所が企業への支援をしているという自負と、顧客満足・顧客感動に向け職員が努力してくれている変化を少なからず感じておりました。こうした個々の企業支援成果はマスコミ沙汰になる様な大きなことでもありませんし、「顧客満足、顧客感動」を目標に研究所運営を進めている者として、それで良いとも思っておりました。
しかし、外から見たとき、当研究所の活動はマスコミなどから知ることしかできないわけで、年賀状を書かれたOBのひと言は、一般県民の感想でもあるわけです。
支援機関は「黒子に徹する」が私の口癖で、決して派手に表舞台に出ることでは無く、企業から感謝され、その企業の業績を伸ばす手助けをすることが「支援機関」の役割と思っておりましたが、今回のことでPRとしての情報発信の必要性も感じた次第です。
情報発信としてはマスコミだけで無く、ホームページでの手段もあるわけで、今後はホームページを通じて、支援成果や活動成果を積極的に進めて行きたいと思います。
ただ、支援機関のあり方として、「マスコミを騒がせる」様な事業をすることが目的ではありませんので、本末転倒することが無いよう注意が必要です。ややもすると、そちらが目的になって「行政主導の企業ニーズ無しの事業」へと走りかねません。支援機関は、あくまで「黒子」で良いというスタンスで、企業に役立つ支援事業を行う姿勢を変えてはいけないと思っています。
今年も、皆様からのご利用をお待ちしております。
顧客満足、顧客感動に向け、職員一同全力で支援をさせていただきます。
12/28 発展するシンガポールから学ぶこと
天皇誕生日の連休を利用してシンガポールへ行ってきました。1回目の訪問が25年くらい前で、それ以来7回くらい行っています。今回は4年ぶりくらいかと思いますが、今回の旅行では、その変貌ぶりに目を見張るものがありました。昔から「クリーン&グリーン」を標語に、綺麗で緑溢れる発展都市でしたが、さらに近代化が進み、コマーシャルで有名な「マリーナ・ベイ・サンズ」の空中プールや、セントーサ島にできたユニバーサルスタジオ、カジノなど(すべて外から見ただけですが)の複合遊戯施設を見て回りました。この国(淡路島程度の面積)が、工業や金融都市、観光都市として発展しており、ものすごい観光客で溢れている様子を見ると、国の施策が明確に解ります。国土や資源が無ければ、何で国民を食べさせて行くか、本気で取り組んだ政治家リー・クワンユ前首相の指導力とその意思を継ぐ現政権(一党独裁の批判もあるが)の力量に脱帽です。
日本も資源が乏しく国土が狭い点はシンガポールと似ており、エネルギー資源のほとんどと食料の約6割は、外貨を稼いで買わなくては国民が生きてはいけません。今度の自民党政権が、どのような経済発展ビジョンを持ち実行できるか、訪問をきっかけにシンガポールと比較してしまいます。
ただ、日本はシンガポールの様な路線を選ぶ必要も無いし、そうあるべきでは無いとも感じています。確かに見た目は非常に発展しているけれども、ソフト面は25年前より劣ってきた感じがし、ホスピタリティ面など人材教育が追いついていない状況でした。
日本が海外にアピールすべきは、シンガポールのようなハード面では無く、ソフト面でさらなる発展をすべきと思います。今、クールジャパンが海外ではブームになっています。観光面なら、「おもてなし」の心や、新鮮な素材を生かした健康的な日本料理、そして清潔で安全な街や自然では無いでしょうか。工業製品であれば、価格勝負の製品では無く、日本人の細やかさを生かした高品質で好感触の製品だろうと思います。そのためには、価格競争の世界から決別し、高くても売れる様な商品開発やブランド戦略を進める必要があると思います。
まだ2回目のブログで今年の最後になりましたが、来年も続けます。
皆様、良いお年をお迎えください。